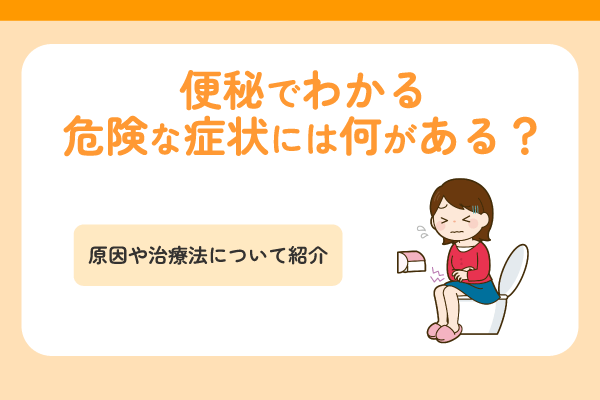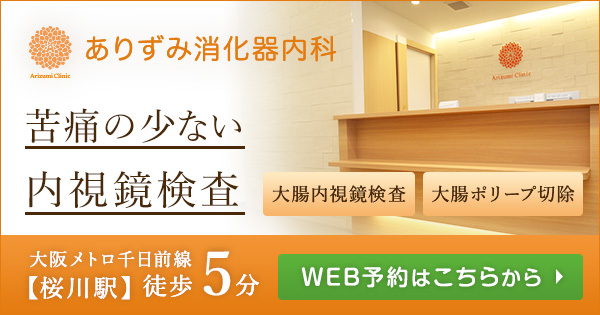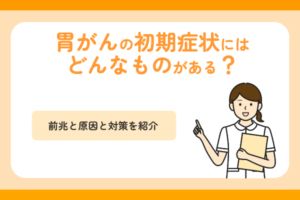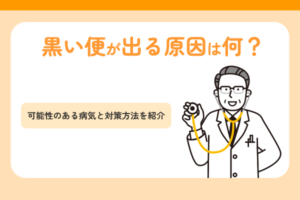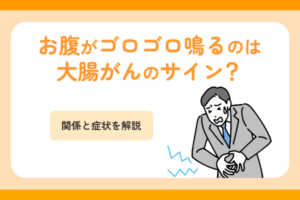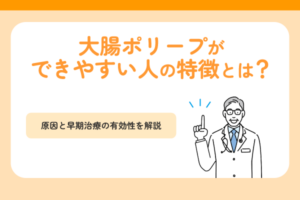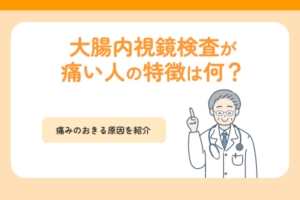「便秘って危険な症状なの?」
「便秘が続いたらがんになりやすいって本当?」
便秘は不快感以外体に痛みがないため軽視する人もいますが、便秘が続いている状態は危険です。
便秘が続いている場合、体に溜まった便が原因で病気を発症するおそれがありますし、逆に便秘の原因は自身の身体になにか問題が発生している可能性があります。
そのため、便秘が続いている場合はその原因を把握し、早急に便秘の解消を目指しましょう。
この記事では便秘に関連する危険な症状についての紹介や、便秘を引き起こす原因、治療方法について紹介します。
便秘気味で悩んでいる方はぜひご参考ください。
- 便秘が原因で発症する危険な症状
- 便秘の原因
- 便秘の治療方法
便秘が関係する危険な症状5選
便秘は単なる生活習慣の乱れだけでなく、重篤な病気のサインとなる場合もあります。
ここでは、便秘に伴って現れる代表的な症状を5つ取り上げ、それぞれの症状が示す可能性のある病態やリスク、対処の必要性について詳しく解説します。
当てはまるものがあれば、早期に適切な行動をとりましょう。
5日以上排便していない
| 異常の種類 | 想定されるリスク |
|---|---|
| 腹部膨満 | 腸管内ガスや便の滞留 |
| 激しい腹痛 | 腸の過伸展・腸管壊死 |
| 便秘の慢性化 | 便秘慢性化による腸内環境悪化 |
排便が5日以上ない状態は、消化器系に深刻な異常が起きている可能性があります。
通常、食後24〜72時間で便は排出されるとされており、それを大幅に超える無排便は「機能性便秘」や「腸閉塞」の兆候として注意が必要です。
とくに便が腸にとどまり続けると、腸管内に老廃物やガスが溜まり、腹部の圧迫感や張り、嘔気などの症状を引き起こします。
さらに、腸内に溜まった硬便が出口付近で詰まると「便塞栓」と呼ばれる状態になり、腸の粘膜を傷つけ出血や激痛を伴うこともあります。
更に、便秘状態が続くことで便秘が慢性化され、上記症状に加えて別の症状が発生するかもしれません。
便秘が慢性化している
| 体の異常 | 想定される影響 |
|---|---|
| 肌荒れ・吹き出物 | 老廃物の蓄積による代謝機能の低下 |
| 肩こり・腰痛 | 有害物質の蓄積による血管の悪影響 |
| 体臭の悪化 | 有害物質の蓄積と毛穴からの排出による悪臭 |
便秘が長期間続いている場合、腸の機能そのものが低下しているか、何らかの病気が隠れている可能性があります。
週に3回未満の排便が3か月以上継続している状態は「慢性便秘」とされ、生活習慣の乱れだけでなく、腸の蠕動運動障害やホルモン異常、腫瘍性病変の影響も懸念されます。
慢性便秘は「排便しづらい状態」が日常化しているため、自覚症状が薄くなりやすく、対処が遅れやすい点が非常に危険です。
慢性化することで上記の症状に加えて、体にも様々な悪影響が現れます。
便が体内にたまり続けることで、便に含まれた有害物質も蓄積してしまいます。
そのため、有害物質は肛門からではなく血管を経由して全身に行き渡ってしまうのです。
その場合、有害物質が血液に混ざることで、血の巡りの悪化による肩こり腰痛や、肌荒れ・吹き出物となって発症します。
更に、有害物質が毛穴から排出されることで、体臭となって他人に不快感を与えてしまいやすくなります。
排便された便に血液が混じっている
| 体の異常 | 想定される影響・背景 |
|---|---|
| 便の中に赤黒い血液が混じる | 大腸の奥・小腸・胃などからの出血 |
| 慢性的なめまいや立ちくらみ | 出血性貧血に伴う酸素不足 |
| 排便後に強い痛みを感じる | 裂肛・痔核による粘膜損傷 |
排便時に血液が混じっている場合、消化管に出血を伴う異常が発生している可能性があります。
もっとも身近なのは痔核(いぼ痔)や裂肛(切れ痔)などの肛門疾患ですが、便に血が混じる場合はその色と形状に注意が必要です。
鮮やかな赤色でトイレットペーパーや便の表面に付着している場合は、肛門周辺からの出血の可能性が高く、比較的軽症です。
一方で、便に血液が混ざり込んでいたり、黒っぽくタール状の便が出た場合、出血部位が大腸や小腸、あるいは胃にまで及んでいる可能性があり、大腸がんや潰瘍性大腸炎などの重大な病気が疑われます。
出血が続くと貧血や酸欠を引き起こすため、「単なる痔かもしれない」と自己判断して放置するのは非常に危険です。
排便されても小さなコロコロした便しか出ない
| 体の異常 | 想定される影響・背景 |
|---|---|
| 排便に強くいきむ必要がある | 便が硬く、排出に時間と力がかかる状態 |
| 便が粒状で乾燥している | 腸内の水分吸収過剰、腸内通過遅延 |
| 排便後もすっきりしない感覚 | 残便感・排便不全による違和感 |
ウサギの糞のような小さく硬いコロコロした便が続く場合、腸内の水分不足や蠕動運動の低下が背景にあると考えられます。
このような便は硬いため、排便のたびに強くいきむ必要があり、肛門への負担が大きくなるため痔や裂肛の原因にもなります。
また、便の滞留時間が長くなることで悪玉菌の増殖が促進され、腸内環境が悪化し、さらに便秘が悪化するという悪循環を招く恐れもあるのです。
腸の働きに影響する病気として、過敏性腸症候群(便秘型)や甲状腺機能低下症が関係していることもあります。
特に甲状腺ホルモンの分泌が少ないと新陳代謝が落ち、腸の動きが鈍化してしまうのです。
便秘と下痢が交互に発生する
| 体の異常 | 想定される影響・背景 |
|---|---|
| 下痢の後に便秘、または逆が続く | 腸の過剰反応、通過障害の疑い |
| 腹部の張りや音が気になる | 腸内ガスの滞留、消化管運動の不安定化 |
| 便意が急に強くなることがある | 自律神経異常や腸粘膜炎症による過敏反応 |
便秘と下痢を繰り返すような排便サイクルの乱れは、腸内の運動や炎症に問題があることを示している可能性があります。
もっとも代表的なのが過敏性腸症候群で、精神的ストレスや自律神経の乱れが腸の働きを不安定にし、排便パターンが極端に揺れ動く特徴を持ちます。
また、大腸ポリープや初期の大腸がんなどでも、腸の一部に通過障害が生じ、便秘と下痢が交互に起こることがあります。
潰瘍性大腸炎では腸粘膜の炎症により排便機能が不安定になり、粘液を伴う便や血便とともに、便性の急激な変化が見られることがあります。
こうした症状は「一時的な体調の乱れ」として見過ごされがちですが、周期性がある場合や長期間続く場合は、腸の器質的異常の可能性も考慮する必要があります。
排便のリズムが安定しない状態は、腸の機能異常を知らせる重要なシグナルです。
生活習慣の見直しだけでなく、身体の内側で起きている変化にも意識を向ける必要があります。
便秘が起きる原因
便秘の背景には、年齢、生活習慣、そして内科的疾患など、さまざまな要因が関係しています。
ここでは、便秘を引き起こす3つの代表的な原因について解説します。
加齢による腸の機能低下、食事や運動などの生活習慣の乱れ、さらには病気に起因する胃腸機能の障害など、それぞれの要因が便秘にどのような影響を与えるのかを確認しましょう。
加齢で便秘のリスクは上がる
年齢を重ねるとともに、便秘のリスクは確実に高まります。
これは単に体力が落ちるからではなく、腸そのものの働きや排便に関わる全身の調整機能が加齢によって低下するためです。
まず、腸の蠕動運動が弱まり、便を押し出す力が不足してきます。
さらに腹筋や骨盤底筋群の筋力も落ち、排便のための腹圧がうまくかけられなくなることも一因です。
これに加えて、加齢とともに水分摂取量が減る傾向があり、腸内の便が硬くなりがちになります。
また、パーキンソン病や脳血管障害などの神経疾患を抱えている高齢者では、自律神経系の働きが乱れやすく、腸の運動が不安定になることがあります。
以下で加齢に伴い起こりやすい体の異常とその背景を整理しました。
| 体の異常 | 想定される影響・背景 |
|---|---|
| 排便頻度の低下 | 蠕動運動の低下、筋力の低下 |
| 便が硬くなり排出に時間がかかる | 水分摂取量の減少、腸内水分不足 |
| 排便時に腹部の圧力を感じにくい | 腹筋・骨盤底筋群の筋力低下 |
このように、高齢者はさまざまな身体機能の低下が便秘につながりやすいため、加齢に応じた予防とケアが非常に重要です。
生活習慣が原因による腸内環境の悪化
乱れた生活習慣は、腸内環境に大きな影響を与えます。
特に、食事の内容や時間、睡眠の質、運動の有無など、腸内環境は様々な要素に影響を受けやすいです。
例えば、朝食を抜くと腸の「胃・結腸反射」が発動せず、排便リズムが狂ってしまいますし、インスタント食品や脂質の多い食事が中心の生活では、食物繊維や発酵食品の摂取が不足し、腸内の善玉菌が減少するおそれがあります。
また、動物性たんぱく質ばかり摂取していると悪玉菌が増え、便秘が慢性化しやすくなるのも注意が必要です。
社会人の場合、慢性的な運動不足や長時間のデスクワークも腸の動きを低下させます。
精神的なストレスが続くと、自律神経のバランスが崩れ、血行が悪くなり、腸内環境にも影響が及ぶ場合があります。
以下で、生活習慣の乱れによって現れやすい体の異常をまとめました。
| 体の異常 | 想定される影響・背景 |
|---|---|
| 便が不定期・リズムが乱れる | 食生活や起床時間の乱れによる影響 |
| 便が臭う・色が濃い | 腸内の悪玉菌の増殖 |
| ストレス時に腹痛や便秘が出る | 自律神経の乱れによる腸の不安定な運動 |
病気が原因で発生する胃腸の機能低下
便秘が病気を引き起こすのとは逆に、病気が便秘を引き起こす可能性もあります。
特定の病気が原因で腸の動きが低下し、慢性的な便秘を引き起こすケースは少なくありません。
とくに内分泌系や神経系の疾患が関与する場合、腸の自律的な運動に障害が生じやすくなります。
便秘を引き起こす病気として考えられるのは、おもに以下の病気です。
- 糖尿病
- パーキンソン病
- 脳関連の疾患
- ポリープ及び胃がん、大腸がんによる腫瘍
たとえば、糖尿病による「自律神経障害」は、消化管の動きに直接影響を与え、胃もたれや便秘といった症状が現れやすくなります。
また、パーキンソン病や脳血管障害などでは、神経伝達の障害により便意を感じにくくなったり、排便機能自体が制御しづらくなることもあります。
胃や大腸にできたポリープは腫瘍が直接便の排出を阻んでいることが多いです。
これらの疾患による便秘は、生活習慣の改善だけでは解消しにくく、医療的介入が必要になるケースも多いのが特徴です。
ここで紹介している病気の他にも、便秘を引き起こす病気は数多くあります。
病気が原因で起こりやすい便秘の症状は、以下のとおりです。
| 体の異常 | 想定される影響・背景 |
|---|---|
| 便意がない、もしくは極端に少ない | 神経系の伝達障害、感覚低下 |
| 常に便秘が続く | 腸の運動機能そのものが低下している状態 |
| 食後も胃が重く、排便が遅れる | 消化機能の遅延、蠕動運動の低下 |
これらの異常がみられる場合、単なる生活習慣の見直しでは不十分なことが多く、病気の早期発見・治療が便秘改善のカギとなります。
当てはまるものがあった場合、早急に消化器内科で診断を受けましょう。
便秘の治療方法
便秘が続く場合、おもに2つのアプローチで改善・治療を行います。
- 軽度の~中度の便秘の場合:生活習慣の改善
- 中度~重度の便秘の場合:消化器内科での診断・治療
ここでは、この2つのアプローチ方法について詳しく解説します。
生活習慣の改善
便秘の初期段階や慢性化を防ぐためには、生活習慣の改善が基本であり、もっとも重要な治療法のひとつです。
とくに重要なのが「食事・運動・水分・排便習慣」の4つです。
この4つを以下のように改善することで、以下の効果が期待できるでしょう。
| 改善する習慣 | 期待できる効果 |
|---|---|
| 食物繊維・発酵食品を多く摂る | 善玉菌の増殖・便の量と柔らかさを改善 |
| 軽い運動を習慣化する | 腸の蠕動運動を促進、腹圧を高める |
| 十分な水分補給を行う | 便を柔らかく保ち、排出しやすくする |
| 毎日同じ時間に排便する習慣をつける | 排便リズムの確立、排便反射の強化 |
まず食事面では、野菜・海藻・豆類などに含まれる「不溶性食物繊維」と、果物やオートミールに含まれる「水溶性食物繊維」のバランスよい摂取が腸内環境の改善に役立ちます。
ヨーグルトや味噌汁などの発酵食品も善玉菌を増やすため効果的です。
ウォーキングやストレッチなどの軽い有酸素運動は腸を刺激し、蠕動運動を活発にします。
特に腹筋を使う運動は排便力の維持に有効です。
加えて、水分不足は便を硬くする大きな要因となるため、1日1.5〜2リットルの水分摂取を目安にしましょう。
そして、毎日同じ時間帯にトイレへ行くなど、排便の「習慣化」も整腸に効果があります。
生活改善による効果はすぐに現れるものではありませんが、継続することで腸内環境が整い、便秘体質を根本から見直すことが可能になります。
重度の便秘は病院で診断と治療を受ける
生活習慣の改善を続けても便秘がまったく解消しない、あるいは急に便通が極端に変化した場合は、便秘の原因が病気にある可能性が高く、生活習慣の改善だけでは解決しません。
病気の場合、消化器内科など専門医による診断と治療が必要です。
病気が原因の場合、早めに判断と診察・治療を受けないと、より症状が悪化し、最悪命に関わるかもしれません。
病気が関連する可能性のある便秘の症状は、以下のとおりです。
| 体の異常 | 医療的介入が必要となる背景 |
|---|---|
| 1週間以上排便がない | 腸閉塞・便塞栓・器質的疾患の可能性 |
| 便に血液・粘液が混じる | 大腸炎・ポリープ・悪性腫瘍の可能性 |
| 腹痛・吐き気を伴う排便困難 | 腸のねじれや閉塞など緊急対応が必要な状態 |
病院では、問診や腹部の触診に加えて、便潜血検査、血液検査、レントゲンや大腸内視鏡などによって、腸内の異常を詳細に調べます。
この検査は適切な治療法を選択するうえで、非常に重要です。
また、便秘が続いて腸内に大量の便が蓄積してしまった場合には、浣腸や経口下剤などの処置が必要になることもあります。
再発を防ぐためには、薬物療法と併行して生活指導や食事療法が行われることも一般的です。
重度の便秘は「様子を見る」で済ませてはならないケースも多く、特に上記のような異常が見られる場合は速やかに医師の診断を受けることが重要です。
判断が早ければその分症状の悪化も未然に防ぎやすくなり、治療期間も短くなります。
まとめ
この記事では、便秘が原因で起きる危険な症状や対処方法について紹介しました。
便秘は日常的な不快感にとどまらず、場合によっては重大な病気のサインとなることがあります。
「排便が5日以上ない」「血便が混ざる」「便秘と下痢を繰り返す」などの症状は、大腸がんや腸閉塞、過敏性腸症候群など、放置してはいけない疾患の可能性を示しています。
これらの異常サインを見逃さず、早期に対処することが健康維持には不可欠です。
「便秘は恥ずかしい」と思う方もいるかも知れませんが、便秘は立派な病気であり、危険な症状です。
早めに判断し、消化器内科に相談しましょう。