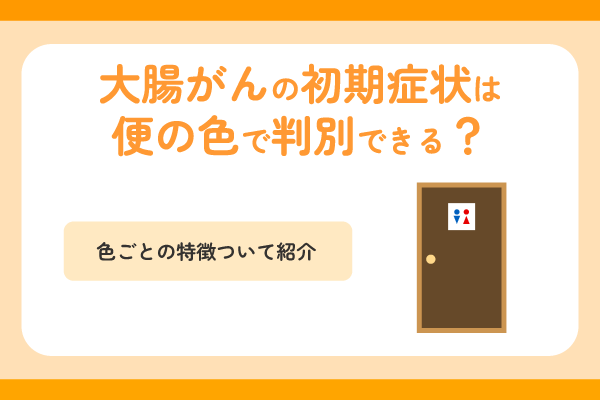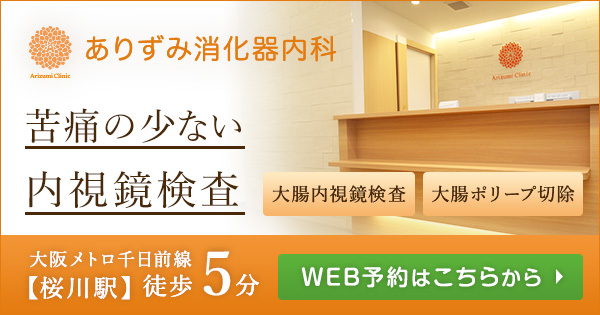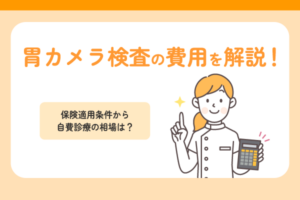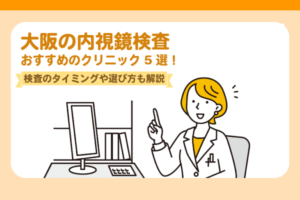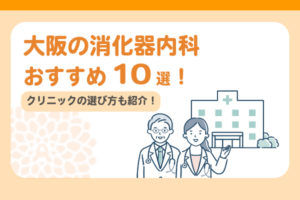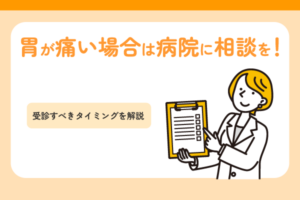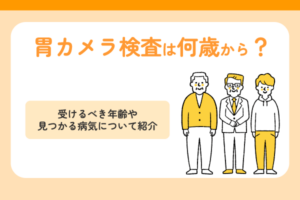「大腸がんは便の色でわかるって本当?」
「普段とは色が違う便が出たけどこれは病気なの?」
結論からいえば、便の色だけでは大腸がんかどうかというのは判別できません。
しかし、大腸がんの初期症状の一つに血便があるため、いつもと違った色の便が出た場合、少し注意が必要かもしれません。
便の色は、健康のバロメーターです。
体に不調がなくても赤黒い便が出たりコロコロと小さな便が出た場合、胃腸に何らかのトラブルが生じている可能性があります。
この記事では、便の色別の健康状態の見分け方や大腸がんの場合の便の色や形、そして病院での診断方法など、様々な事柄を紹介します。
- 便の色と健康状態
- 大腸がんの場合の便の色
- 消化器内科で行う検査方法
便の色は胃腸の調子を教えてくれる
便の色は、消化器系の健康状態を示す重要なサインです。
正常な黄土色の便と比べて、異常がある場合は色に変化が生じることがあります。
色が変化する理由としては、血液が付着していたり、あるいは便に色がつかなくなったりといったことが原因です。
病気の可能性を早期に見つけるためにも、便の色と健康状態を把握しましょう。
ここでは、便の色が示す内臓の問題について、色別に紹介します。
胃腸の状態が健康的な場合は黄土色
健康な消化器系では、便は黄土色を呈します。
これは、胆汁と消化された食物が混ざり合うことで生じる自然な色です。
食事のバランスが良く、消化吸収が正常に行われている証拠といえます。
黄土色の便が継続している場合、胃腸が健康的に機能していると考えてよいでしょう。
食べ過ぎや消化不良の場合は濃褐色あるいは緑色
- 食べ過ぎ
- 急性腸炎
食べ過ぎや消化不良が起こると、便の色が濃褐色や緑色に変化することがあります。
濃褐色の場合は肉類やカカオ、緑色の場合は野菜の食べ過ぎが原因で色が変化します。
例えば、野菜を食べすぎた場合、野菜に含まれている葉緑素が便に付着し、緑色になります。
この場合、色が変化するのは一時的なものなので、1日程度でもとの色に戻るでしょう。
食べ過ぎではない場合、病気か何かで腸の働きが鈍っていると、便に色を付ける成分であるビリルビンがうまく分泌されなくなり、緑色に見えてしまいます。
一時的なものであれば問題ありませんが、長期間続く場合は、腸内環境を改善するために食生活の見直しをおすすめします。
肝臓や胆管に問題がある場合は白色
- 黄疸
- 肝不全
- 感染性腸炎
- 胆石
など
肝臓や胆管に異常があると、便が白色や灰白色になることがあります。
これは、胆汁の分泌や排出に問題が生じ、便に色をつけるビリルビンが不足することによるものです。
胆石症や肝炎、胆道閉塞などが原因となることがあります。
この場合、大腸がん並に深刻な症状である可能性があります。
肝不全は肝臓機能がうまく働いていないということであり、体内の老廃物が排出されず、毒素が体に溜まってしまう状態です。
また、アンモニア濃度も高まり、脳機能の障害や昏睡状態に発展することもあります。
問題のないケースとしては、バリウム検査後に数日間出る便です。
これは、造影剤として使用したバリウムが便に混ざることで白色になる状態です。
こちらは早めに排出しないとバリウムが腸内部で固まってしまうため排出されにくくなるので、検査後に処方された下剤を使用し、早めに排出しましょう。
内臓に出血がある場合は赤や黒色
- 痔
- 胃腸炎
- 胃潰瘍、十二指腸潰瘍
- 胃がん、大腸がん
など
消化管内で出血が起こると、便が赤色や黒色に変化することがあります。
鮮やかな赤色の便は、直腸や肛門付近の出血を示し、黒色の便は上部消化管での出血を示す可能性があります。
これは、血液が付着してから経過した時間が関係します。
痔の場合、肛門付近で出血したため付着した時間は少ないため、鮮やかな赤であることが多いです。
胃腸炎や大腸がんといった胃や腸で出血していた場合、血液が便に付着してから排泄されるまで長い時間がかかるため、血液に含まれたヘモグロビンが酸化し、赤黒く変色します。
そのため、胃腸に問題がある場合、赤黒いどろっとした色の便が排出されます。
この状態の便が出た場合、速やかに医師の診察を受けることが必要です。
大腸がんの場合の便の色は何色?
大腸がんの便の色には特有の特徴はありませんが、血便や便の形状の変化が見られることがあります。
特に血液が混じることで便の色が変化するため、日々の観察が重要です。
ここでは、大腸がんと便の色の関係について説明します。
大腸がん特有の便の色はありません
上述したように、大腸がん特有の便の色はありません。
胃炎でも十二指腸潰瘍でも同様に赤黒い色の便です。
注意しなければならないのは、便の色だけではなく、便の形や排便の習慣です。
大腸がんは、腸に悪性腫瘍が発生する病気です。
そして、腫瘍によって便に様々な異常が発生します。
| 症状 | 理由 |
|---|---|
| 排便習慣の変化 | 腫瘍によって便の排出が困難になるほか、水分吸収能力が低下することにより、下痢と便秘が交互に発生する |
| 便の形状変化 | 腸管の狭窄による便が細長くなったり、小さなコロコロとした便になってしまう |
| 残便感 | 便が排出されにくくなるため |
| 出血 | 腫瘍に便がこすれることで腫瘍から出血 |
もし、トイレでこういった状態が慢性的に続く場合、消化器内科で相談しましょう。
血便が出た場合は要注意
血便が出て、その便の色が黒いどろっとした便だった場合は注意が必要です。
上述したように、赤黒い便は胃腸から出血して便に付着している可能性が高く、大腸がんでないにせよ、胃腸炎を患っている可能性があります。
定期的な痛みや嘔吐感を感じている場合、胃潰瘍や胃腸炎である可能性が高いでしょう。
なお、痛みや嘔吐感がない場合、大腸がんを疑ったほうが良いかもしれません。
大腸がんは自覚症状の少ない病気の一つであり、痛みや嘔吐感を覚えるのは症状が進行してからのことが多いです。
逆に、便にしか異常がない場合、大腸がんはごく初期の段階である可能性が高いです。
その場合、早期に消化器内科で診断を受け、がんだった場合早期治療で安全に治療できるかもしれません。
体に痛みがなくても便に異常があった場合、消化器内科の受診をおすすめします。
消化器内科での検査方法
大腸がんの早期発見には、定期的な検査が有効です。
消化器内科で行われる主な検査方法を以下に紹介します。
早期発見により治療の選択肢が広がるため、定期的なチェックを心がけましょう。
便潜血検査
便潜血検査とは、名前の通り便中の微量な血液を検出する検査方法です。
目に見えない出血を発見することができ、大腸がんのスクリーニングとして広く用いられています。
便潜血検査そのものでは、大腸がんと識別することはできませんが、陽性反応が出ることで初期症状の段階で病気を発見するきっかけを作ることができるのが、便潜血検査の特徴です。
陽性結果が出た場合は、さらに詳しい検査が必要となり、そこから胃腸の状態をより鮮明に知ることができます。
また、定期的に受けることで、がんの早期発見につながります。
大腸バリウム検査
大腸バリウム検査は、バリウムという造影剤を用いて大腸の形状や異常をX線で確認する検査です。
健康診断で行われることが多い検査であり、ポリープや腫瘍の有無を調べることができます。
内視鏡検査に比べて精度が劣るため、異常が見つかった場合は内視鏡検査が推奨されます。
また、検査の際に腸の動きが鈍くなることがあるため、事前に医師と相談することが大切です。
内視鏡検査
内視鏡検査は、口や鼻、または肛門から内視鏡を挿入し、大腸内を直接観察する検査です。
いわゆる胃カメラ検査であり、現在では内視鏡が使用されています。
ポリープや腫瘍を直接確認でき、その場で組織を採取したり、ポリープを切除する内視鏡手術も可能です。
内視鏡検査は大腸がんの診断や治療において最も信頼性の高い検査方法です。
また、定期的に受けることで、大腸がんの早期発見・予防につながります。
まとめ
この記事では便の色と健康状態、そして検査方法や大腸がんの症状などについて紹介しました。
便の色の変化は、消化器系の健康状態を知る重要な手がかりになります。
特に血便や異常な色の変化が見られた場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
定期的な検査を受けることで、大腸がんのリスクを減らし、健康な生活を維持することが可能です。