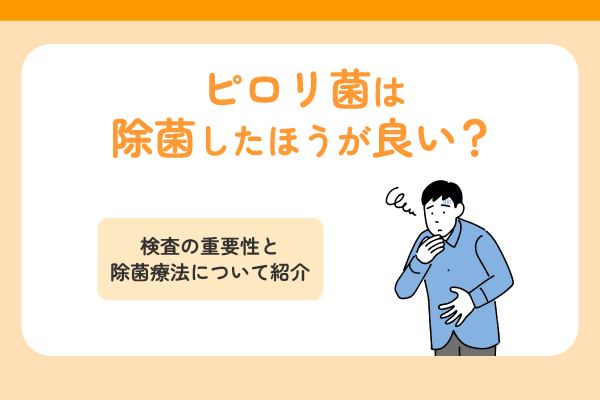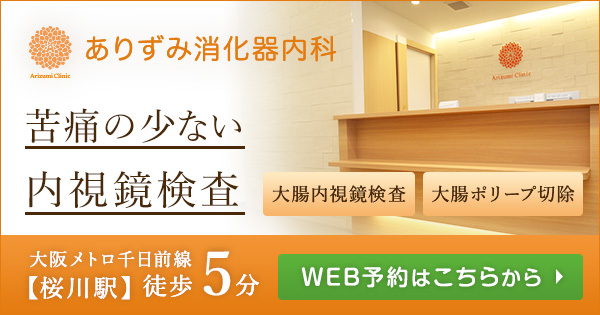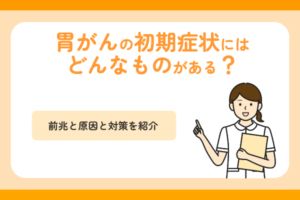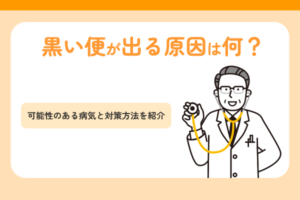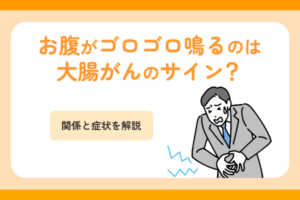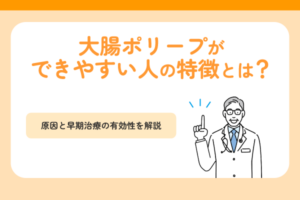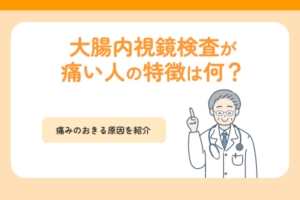「ピロリ菌は除菌した方が良いの?」
「そもそもピロリ菌って何?」
ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)とは、胃の粘膜に生息する細菌で、胃炎や胃潰瘍、胃がんなどの消化器疾患の原因となることが知られています。
今でこそ感染者は減少傾向にあり、2000年代生の人なら感染者は6%前後ですが、それでもピロリ菌に感染していると、様々な病気のリスクが発生します。
ピロリ菌は感染していても初期の段階では自覚症状がないため放置されがちですが、放置した場合胃癌のリスクが増大するため、早期に対処したほうが得策です。
そんなピロリ菌は適切な検査を行うことで感染の有無が確認できますし、治療によって除菌することも可能です。
この記事では、ピロリ菌によって起きる症状のリスクや治療方法について紹介します。
- ピロリ菌が原因で起きる症状
- ピロリ菌の検査方法
- ピロリ菌の除菌方法
ピロリ菌の起こす病気
ピロリ菌は、胃の粘膜に生息する細菌であり、感染が持続するとさまざまな消化器疾患を引き起こします。
ピロリ菌は鞭毛と呼ばれる体毛を旋回して移動することから「ヘリコバクター」という名前がついており、胃液から身を守るためのアンモニアを分泌し、胃酸を中和しています。
このアンモニアが胃腸に様々な症状をもたらす他、鞭毛が胃壁を傷つけることが、ピロリ菌が様々な病気を引き起こすと考えられています。
ここでは、ピロリ菌感染が関係する主な疾患について解説し、それぞれの発症メカニズムを説明しましょう。
ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎
ピロリ菌が胃に感染すると、まず慢性炎症が起こります。
これは「ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎」と呼ばれ、放置すると胃の粘膜が傷み、次第に萎縮していく症状です。
さらに進行すると、正常な胃の粘膜が腸のような組織に変化する「腸上皮化生」と呼ばれる症状が起きます。
これは胃がんになるリスクを高めてしまう恐ろしい症状であり、こうした経過をたどることで、無症状であっても将来的に大きなリスクを抱えることになります。
ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎は、以下のように進行し、病気の発生リスクを高めます。
| 病変の進行段階 | 病理的変化 | 症状 |
|---|---|---|
| 感染性胃炎 | ピロリ菌による粘膜の炎症 | 自覚症状は少ないが慢性化 |
| 萎縮性胃炎 | 胃酸・消化酵素の分泌能力低下 | 消化不良や栄養吸収障害 |
| 腸上皮化生 | 腸の粘膜様の細胞に置換 | 胃がん発症の前段階 |
胃潰瘍
ピロリ菌が胃酸の分泌を過剰に刺激したり、胃の粘膜を傷つける酵素を分泌することで、粘膜が深くえぐれる潰瘍が形成されます。
潰瘍とは胃炎が悪化した症状を指します。
胃炎というのは胃を保護する粘膜の炎症ですが、潰瘍とは粘膜を通過し、胃壁が直接炎症を起こしている状態です。
そのため、胃炎に比べると数ヶ月単位で治療に時間がかかるだけではなく、胃痛や吐き気なども悪化していきます。
胃潰瘍の中でも特に十二指腸潰瘍は、ピロリ菌感染者の多くに認められる疾患であり、繰り返し再発するケースもあります。
潰瘍による症状は、みぞおちの痛みや空腹時の胃もたれ、出血による貧血などがあり、自然治癒も難しくなるでしょう。
なお、胃潰瘍と十二指腸潰瘍はそれぞれ症状が異なりますので注意しましょう。
| 比較項目 | 胃潰瘍 | 十二指腸潰瘍 |
|---|---|---|
| 主な発症部位 | 胃の下部(幽門部) | 小腸の入口(十二指腸) |
| 主因 | ピロリ菌・NSAIDs | 主にピロリ菌 |
| 主な症状 | 鈍い胃痛、吐血 | 空腹時の強い痛み、黒色便 |
| 治療方針 | 除菌と胃酸抑制 | 除菌と生活指導 |
特発性血小板減少性紫斑病(ITP)
特発性血小板減少性紫斑病(ITP)とは、血液中の血小板が異常に減少する疾患で、皮膚や粘膜に紫斑が現れたり、出血が止まりにくくなる症状が見られます。
原因不明とされることも多いITPですが、近年ではピロリ菌との関係が明らかになりつつあります。
ピロリ菌の除菌で症状の改善が出た例は多く、発症した場合はピロリ菌の検査を行ったほうが良いかもしれません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発症原因 | ピロリ菌感染が免疫系を刺激し、血小板を攻撃する抗体が産生される |
| 主な症状 | 皮膚出血、鼻血、歯茎からの出血、月経過多など |
| 除菌の効果 | 除菌によって30〜60%の症例で血小板数が改善 |
胃がん
ピロリ菌感染は、胃がん発症の主要な原因の一つとされており、世界保健機関(WHO)もこの関連を明確に認めています。
感染が長期間にわたって持続することで、萎縮性胃炎や腸上皮化生といった前がん状態を経て、最終的に腺がんが発生します。
特に日本では、ピロリ菌保有率が高かった世代を中心に胃がんの発症率も高いため、予防の観点からも除菌は非常に重要とされます。
症状が進行するまで現れにくいことが多いため、ピロリ菌感染の早期発見と除菌が、最も有効な一次予防策となります。
そんな胃がんですが、ピロリ菌の感染と同じく、自覚症状が初期段階ではほぼありません。
自覚症状が現れ始めるのはステージが進行した段階であり、完治の確率が大幅に下がってしまいます。
しかし、初期段階でピロリ菌の発見や胃がんを確認できた場合、9割の確率で治療は成功すると言われており、初期段階から次のステージに進むまで年単位の時間があります。
そのため、定期的な検査を行えば胃がんのステージが進行するリスクは大幅に下げられるでしょう。
ピロリ菌の有無は消化器内科で検査する
ピロリ菌感染は自覚症状が少ないため、感染していても気づかずに長期間放置されることがあります。
感染の早期発見には、適切な検査が欠かせません。
検査方法には、内視鏡を使って胃の粘膜を直接調べる精密検査と、体への負担が少ない非内視鏡的な方法の2種類があります。
ここでは、それぞれの検査方法の特徴や選び方、精度についてわかりやすく解説しましょう。
内視鏡検査を用いて行う検査方法
ピロリ菌検査で一般的なのは、内視鏡を用いた検査です。
内視鏡を用いた検査は、胃内の粘膜を直接観察できるのが最大の特長です。
粘膜の状態を視覚的に確認できるため、胃炎や潰瘍、がんの兆候も同時に発見することが可能なため、短期間でピロリ菌の有無と胃がんの検査が終わるというのは、内視鏡検査ならではの強みでしょう。
さらに、内視鏡検査では生検として胃の粘膜の一部を採取し、ピロリ菌の有無を以下の方法で調べることができます。
| 検査法 | 方法 | 特徴 | 判定速度 | 精度 |
|---|---|---|---|---|
| 迅速ウレアーゼ試験 | 胃粘膜に尿素を加えてpH変化を観察 | 安価・簡便 | 数分〜1日 | 高い |
| 鏡検法 | 顕微鏡で菌の形態を直接確認 | 技術を要する | 数日 | 非常に高い |
| 培養法 | 菌を人工的に増殖させて確認 | 最も確実だが時間がかかる | 数日〜1週間 | 非常に高い |
これらの検査は診断の精度が高いため、症状がある方や、過去に胃の異常を指摘された方には推奨されます。
特に胃がんのリスクが懸念される40歳以上では、内視鏡検査の併用が重要です。
内視鏡検査をせずに行う検査方法
ピロリ菌検査は、内視鏡を使用しなくても可能です。
内視鏡はたしかに確実性が高いですが、胃カメラを体に通すのに抵抗感があり、二の足を踏む人は少なくありません。
内視鏡に抵抗がある方や、スクリーニング目的で検査を希望する方には、非内視鏡的な方法が適しています。
体への負担が軽く、簡便な方法でありながら、精度も一定レベルで保たれています。
| 検査法 | 方法 | 対象 | 特徴 | 判定時間 | 精度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尿素呼気試験(UBT) | 尿素を服用し呼気中の二酸化炭素の変化を調べる | 感染の有無 | 非侵襲的・高精度 | 当日〜翌日 | 非常に高い |
| 血中抗体検査 | 血液でピロリ菌抗体の有無を調べる | 現在または過去の感染 | 検診で使用されることが多い | 数日 | 中程度(古い感染も検出) |
| 便中抗原検査 | 便に含まれるピロリ菌の抗原を調べる | 現在の感染 | 自宅でも可能、除菌判定にも有効 | 数日 | 高い |
特に尿素呼気試験は、ピロリ菌の現在の感染状態を正確に評価できるため、初回の診断にも除菌判定にも使われています。
一方で血中抗体検査は過去の感染も検出するため、陽性でも現在の感染とは限らない点に注意が必要です。
ピロリ菌の検査方法は、精度・侵襲性・費用のバランスによって選択肢が分かれます。
症状がある場合は内視鏡を併用し、健康診断や家族歴がきっかけで心配な場合は非内視鏡的検査からスタートするのも良い判断です。
ピロリ菌の除菌方法について
ピロリ菌の感染が確認された場合、将来的な胃がんなどのリスクを減らすためにも、除菌治療を検討することが重要です。
除菌は、薬を服用することで体内からピロリ菌を排除する治療法であり、一定の成功率と再発防止効果が確認されています。
ただし、副作用のリスクや再除菌が必要なケースもあるため、治療の仕組みや注意点を正しく理解しておくことが必要です。
ここでは、除菌療法の内容とその効果、副作用について詳しく解説します。
ピロリ菌は薬を飲んで除菌する
ピロリ菌の除菌治療では、複数の薬を組み合わせた「三剤併用療法」が行われます。
主に、胃酸の分泌を抑えて抗生物質の効果を高めつつ炎症を和らげる薬と、ピロリ菌を除菌するための2種類の抗生物質を1日2回、7日間服用するのが標準的な方法です。
薬は指定の期間・用量を正しく服用することで、高い除菌成功率が得られます。
| 薬剤区分 | 目的 |
|---|---|
| 胃酸分泌抑制薬 | 胃の酸を抑えて抗菌薬の効果を高める |
| 抗菌薬① | ピロリ菌の細胞壁を破壊 |
| 抗菌薬② | タンパク合成を阻害し殺菌 |
この一次除菌での成功率は約70〜80%とされており、失敗した場合は「二次除菌」として使用する薬品を変更するなどの再処方が行われます。
二次除菌の成功率は90%以上と高く、再度失敗した場合はさらに第三の抗菌薬を用いた「三次除菌」も考慮されます。
除菌療法で副作用が出る場合もある
除菌療法は基本的に安全性の高い治療法ですが、一部の患者では副作用が発生する可能性があります。
症状の程度は軽いものから重いものまで様々であり、早期の対処が重要です。
副作用が出ても自己判断で中断せず、医師と相談しながら対処しましょう。
よく見られ副作用と対処法は、以下のとおりです。
| 副作用 | 主な症状 | 対応の目安 |
|---|---|---|
| 下痢・軟便 | 水様便、腹部の張り | 軽度であれば服薬を継続可 |
| 味覚異常 | 食べ物の味が変わる、金属の味がする | 通常は一時的で治療終了後に回復 |
| 発疹・かゆみ | 皮膚に赤みや湿疹 | 重度の場合は服薬中止、すぐに受診 |
| 発熱・倦怠感 | 微熱やだるさが続く | 感染症や薬剤アレルギーの可能性あり |
副作用の多くは一過性のもので、治療完了とともに自然に軽快しますが、異常を感じたら早めに医師に連絡を取りましょう。
また、ピロリ菌除菌後には腸内細菌バランスが変化するため、整腸剤の併用や発酵食品の摂取も効果的です。
まとめ
この記事では、ピロリ菌の症状や検査方法、治療方法を紹介しました。
ピロリ菌の感染は、日常生活では気づきにくい一方で、放置すると将来的に深刻な疾患につながる可能性があります。
感染が見つかった場合は適切な除菌療法によって健康な胃を保つことができ、治療にかかる手間も短期間です。
胃の健康は、消化機能だけでなく全身のコンディションにも影響します。
ピロリ菌に対する正しい知識を持ち、早期の対応を心がけることが、長く健康で過ごすための確かな一歩です。
なお、ピロリ菌の感染経路は主に経口感染であり、清潔さが保たれていない状態の水を飲むことで感染すると考えられています。
そのため、現在の20代の人の感染率は6%程度と極めて微小ですが、今より水道設備が整っていない40~60歳の世代の場合、感染率は40%を超える場合があります。
40代以降の人は、自治体によっては胃腸の検査を安価もしくは無料で行うことができるので将来の健康のためにも定期的な検査をおすすめします。