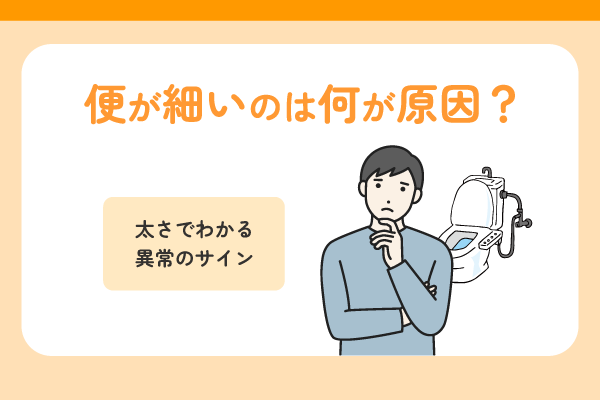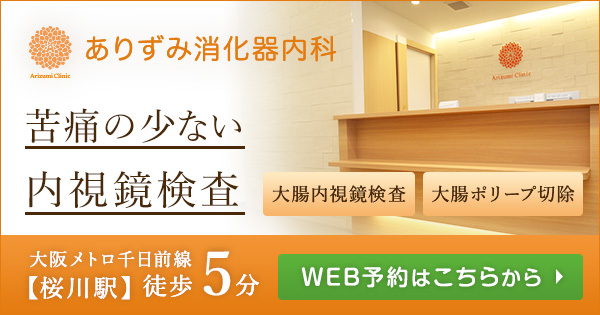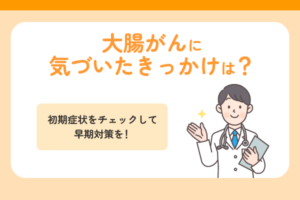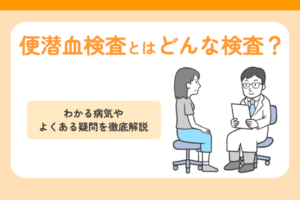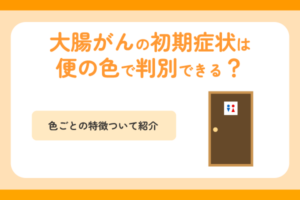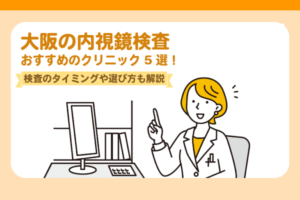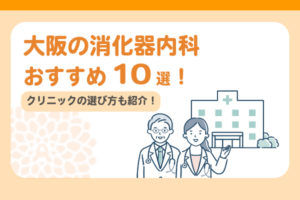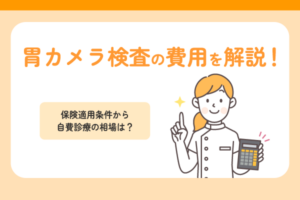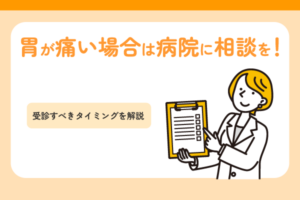「最近便が細い気がするが、お腹の異常だろうか?」
「便が細いと病気のサインと聞くが、本当だろうか?」
いつもより便が細いとお腹の調子を気にする人は多いです。
便が細い原因の多くは便秘や生活習慣の乱れですが、病気が原因でも便は細くなります。
基本的に、1日や2日程度便が細いだけであれば病気の心配はそこまでしなくてもよいですが、一週間以上続いたり、他にもお腹の調子が悪かったりした場合は、病気を疑ったほうが良いかもしれません。
この記事では、細い便が出る原因や、便から考えられる病気、そして対処方法を紹介します。
- 便が細くなる原因
- 便の状態から考えられる健康状態と症状
- 細い便が続いた場合の対処方法
細い便が出る原因は何?
細い便が出る理由を大きく分けると、おもに次の3つに分類されます。
- 病気で腸の一部が狭くなっている
- 生活習慣の乱れによる胃腸内の異常
- 加齢による消化機能の衰え
基本的に、1~2日で改善することが多いのは生活習慣であり、病気、加齢が原因の場合、本格的な対策が必要になります。
ここでは、この3つについて詳しく説明しましょう。
腸の一部が狭くなっている
便が細くなった理由が病気の場合、腸の一部が狭くなり、その過程で便が細くなってしまう傾向にあります。
例えば、大腸ポリープ(腫瘍)が発生することで狭くなることがありますし、胃腸炎によって腸が炎症を起こしている場合、腫れてしまっているため便の通り道が細くなり、結果的に細くなってしまうのです。
もし、病気が原因の場合、胃腸炎のような炎症を起こしている場合は、血便や腹痛、下痢などの症状を伴うことが多いため、便が細くなる理由が病気だと判別しやすいです。
一方、ポリープは基本的に無症状であり、体は元気なのに便が細いということは珍しくありません。
また、ポリープ自体もほとんどの場合は放置して問題ありませんが、ポリープが変異して悪性腫瘍、つまり癌になる可能性もあります。
といっても、ポリープの段階であれば進行も極めて遅いため、すぐに対処しなければいけないというわけではありません。
ですが、もし、次に紹介する不摂生や加齢でも該当しない場合は、病院で相談することをおすすめします。
腸だけではなく、肛門が狭くなってしまい、便が細くなるケースもあります。
これは、主に切れ痔が原因です。
切れ痔は肛門が傷ついている症状であり、治癒の過程で引きつれ(外傷箇所が盛り上がり、締まることで周囲の組織が引っ張られること)を起こすことで肛門が小さく、固くなりやすくなり、結果的に便が細くなります。
もちろん、一回や二回の切れ痔で便が細くなることはなく、何度も切れ痔になることで結果的に狭くなるので、切れ痔を頻発していなければ心配する必要はありません。
摂取した栄養に偏りがある
多くの場合で当てはまるのが、食生活の乱れによる栄養の偏りが原因で、腸内環境が乱れることによるものです。
これが原因に当てはまりやすいのは、以下の人です。
- 脂質を摂りすぎている人
- 食物繊維が不足している人
- ダイエットをしている人
腸内環境が乱れる原因は、食べた食事を分解する腸内細菌のバランスが乱れることが原因にあります。
腸内には、腸の動きを活発にする善玉菌と食べ物を便に変えて体外に排出する悪玉菌と、腸内の勢力が強い方に味方する日和見菌があります。
悪玉菌も腸内環境の維持に必要な存在なのですが、脂質やタンパク質を餌に増殖し、多すぎると腸内に炎症を起こしてしまうという特徴を持っています。
そのため、脂質を取りすぎると悪玉菌の働きが優勢になり、腸内を炎症させやすくなってしまうのです。
一方で、ダイエットにより脂質を抑えすぎると、便の滑りが悪くなり、排便時に肛門で圧縮されて細くなることがあります。
また、食物繊維の不足は便の形成に影響を及ぼし、便が細くなりやすいです。
食物繊維は腸内で水分を吸収し、便のかさを増す役割があります。不足すると便が小さくなり、細くなることがあります。
このように、食事による栄養の偏りは腸内環境の悪化を招きやすく、便が細くなる原因を作ってしまいます。
加齢が原因で便は細くなる
年を取り、体が衰えることで便は細くなりやすくなります。
加齢によって筋肉が衰えることにより、便が出しづらくなっていることが原因です。
他にも、腸の機能の衰えによって蠕動運動が弱くなると、便が腸内に長く留まりやすくなります。その結果、水分が過剰に吸収され、便が硬くなり、細くなることがあります。
また、食事量が減ることによって食物繊維の摂取量が減るというのも、人によっては加齢が原因で便が細くなる原因の一つです。
加齢が原因で便が細くなるのは、基本的に心配することはありません。
しかし、どうしても気になる場合は消化器内科で相談をしましょう。
自治体によっては、40歳以上の場合は腸内の検査が安価で行える場合もあります。
便は体の健康のバロメーター
便は、腸内の健康状態を把握するバロメーターとして、非常に重要な存在です。
擦り傷や切り傷といった外傷なら直接目で見ることができますが、胃潰瘍や大腸がんといった内臓の症状や状態は、内視鏡検査でなければ確認できません。
そのため、健康な便の状態を把握しておけば、体調に異常が出た場合、病院に行くかどうかの判断がしやすいです。
ここでは、そんな便について、健康な便と不健康な便の違いについて説明します。
健康な便は3~4センチの太さとバナナ程度の長さ
健康な便の理想的な形は、バナナのような長さと適度な太さが理想だとされています。
具体的なサイズを言うと、理想的な太さは3~4センチとされており、長さは15~20センチほどです。
これは、腸が細くなっているので便も細くなっているわけではなく、何より水分、食物繊維を摂取しているため便が固くなく、ちぎれていないことの証明になります。
便の色や形でお腹の状態がわかる
長さや太さ以外にも、色や形で胃腸の状態をある程度把握できます。
形については上述したとおり、健康な状態の便は太く長いです。
しかし、水分不足や便秘、胃腸が荒れている場合、便は細くなったり兎の糞のようにコロコロとした状態で排出されやすくなります。
また、色も重要です。
健康な便は黄褐色から茶色をしております。
これは大腸だけではなく、栄養の代謝に欠かせない臓器である肝臓が正常に働いている証拠となります。
しかし、便の色が白い場合は肝臓の働きが鈍っている証拠となり、病院での検査が必要になります。
また、胃潰瘍やポリープが発生している場合、黒い便が出ることがあります。
これは、便が腸の炎症している箇所やポリープに接触することで軽く出血し、血液が便に付着するのが原因です。
細い便が出る原因となる病気
もし、細い便が出る原因が病気の場合、上述したようにポリープや胃腸炎、そして大腸がんなどが考えられます。
ここでは、細い便が出る原因となる病気の中でも代表的なものを3つご紹介しましょう。
切れ痔
切れ痔は、肛門周辺の皮膚が裂けることによって起こる病気です。
排便時に痛みを感じるため、便を細くしようと無意識に力みを抑えることで、細い便が出ることがあります。
切れ痔の原因としては、硬い便による刺激や、慢性的な便秘が挙げられます。
また、切れ痔が悪化すると出血や炎症を伴い、排便のたびに強い痛みを感じることもあり、生活に悪影響が起きやすいです。
今回紹介する症状の中では比較的軽度ですが、症状が悪化すると手術を行う必要も出てくるため、治療後は予防に努める必要があります。
便が細くなる原因が切れ痔である場合は、食生活の見直しが必要です。
特に、食物繊維や水分をしっかり摂取し、便を柔らかく保つことが重要です。
大腸炎
大腸炎は、大腸の粘膜が炎症を起こす疾患で、潰瘍性大腸炎やクローン病などが含まれます。
これらの疾患は、炎症を起こすことで腸が細くなってしまうため、細い便の原因となることがあります。
大腸炎の症状としては、下痢や腹痛、血便などが挙げられます。
大腸炎は、早めに原因の特定と対処、そして治療が必要になる病気です。
大腸炎は粘膜だけの炎症で済んでいる状態ですが、悪化すると潰瘍に発展し、数ヶ月単位で治療期間が伸びてしまうからです。
更に、改善せずに悪化していくと、今度はがんに発展する可能性があります。
炎症を起こす理由としては、ストレスによる胃酸過多や食生活の乱れによる悪玉菌の増殖が主な要因として挙げられます。
医師と相談し、生活習慣の見直しをしましょう。
胃がん
大腸に関連する病気の中でも特に注意が必要になるのが、大腸がんです。
生活習慣や食生活の見直しをしても自然治癒をすることはなく、正しい治療を受けなければ命の危険に関わります。
大腸がんは、初期段階では痛みや吐き気など自覚症状がほとんどないことが特徴ですが、進行すると腸の狭窄を引き起こし、便が細くなることがあります。
特に、血便や急な便通の変化が見られる場合は、早急に医療機関を受診する必要があります。
放置していると、他の内臓部位にがんが転移してしまうため、早期対処が必要です。
大腸がんのリスクを減らすためには、バランスの取れた食事、定期的な運動、適切な健康診断が重要です。
早期発見が治療の鍵となるため、便の変化に敏感になることが大切です。
細い便が続く場合は病院で相談しよう
便が細い状態が長く続く場合、単なる食生活の乱れだけでなく、腸に異常が起きている可能性があります。
自己判断で放置せず、適切な診断を受けることが重要です。
ここでは、細い便が続く場合に受診すべき診療科と、検査方法について詳しく解説します。
消化器内科で検査を受ければ原因がはっきりしやすくなる
細い便が続く場合、消化器内科を受診して検査を受けることで、原因を特定しやすくなります。
医師は便の形状や色、排便の頻度などを確認し、必要に応じて大腸内視鏡検査や血液検査を行います。
特に、大腸がんや大腸炎などの疾患が疑われる場合、早期の発見と適切な治療が重要です。
また、検査によって異常が見つからなかった場合でも、食生活や生活習慣の見直しが推奨されることがあります。
定期的な検査を受けることで、腸の健康を維持しやすくなります。
病気の場合は適切な治療を受けよう
消化器内科の診断で病気が判明した場合、早急に適切な治療を受けることが重要です。
例えば、大腸がんが原因の場合、手術や放射線治療、化学療法などの治療法が選択されます。
一方、炎症性腸疾患が原因である場合は、薬物療法や食事療法を取り入れることで症状の改善が図られます。
また、軽度の疾患であっても放置せず、医師の指導に従って適切な治療を受けることが健康維持につながります。
定期的な健康診断を受け、異常があれば早めに対処することが重要です。
日常生活の見直しで細い便の解消が可能
生活習慣の改善も、細い便の解消につながります。
特に、以下のポイントに注意すると、腸内環境を整えることができます。
- 食物繊維の摂取(野菜、果物、全粒穀物を意識的に摂る)
- 水分補給(1日1.5~2リットルの水を飲む)
- 適度な運動(ウォーキングやヨガで腸を刺激)
- ストレス管理(リラックスする時間を確保)
これらの対策を実践することで、腸の健康を維持し、便の形状を整えることができます。
細い便が続く場合は、単なる生活習慣の影響だけでなく、腸の病気が潜んでいる可能性もあるため、早めに専門医に相談することが重要です。
まとめ
この記事では、細い便が出る原因や対処方法について紹介しました。
便の太さや形状は、腸内環境や健康状態を反映する重要な指標です。
細い便が一時的に発生することはありますが、長期間続く場合は何らかの異常が関与している可能性があります。
腸の狭窄や食生活の乱れ、加齢、さらには大腸炎や大腸がんといった疾患が細い便の原因となることがあります。
そのため、生活習慣の見直しを行うとともに、異常が続く場合は消化器内科を受診し、適切な検査を受けることが大切です。
日常的に食物繊維を多く含む食品を摂取し、十分な水分補給と適度な運動を心がけることで、腸内環境を良好に保つことができます。
便の変化を見逃さず、健康管理の一環として定期的にチェックする習慣を身につけましょう。