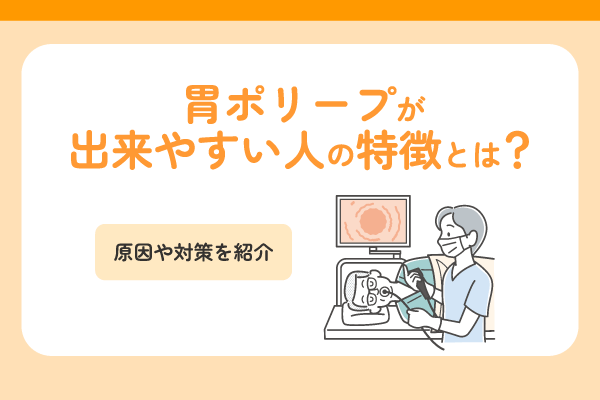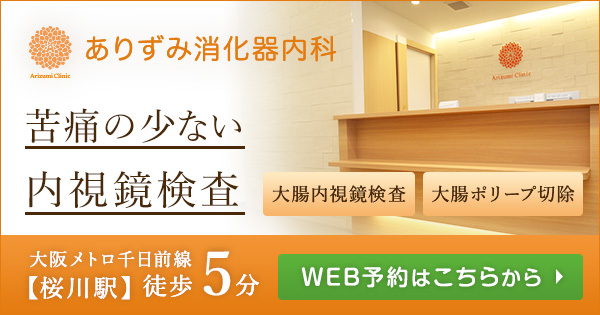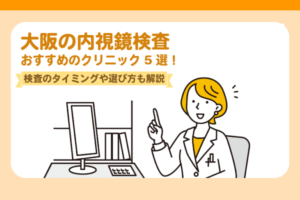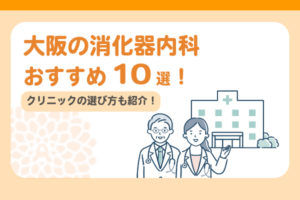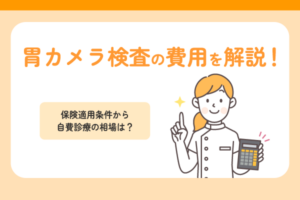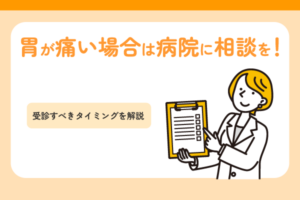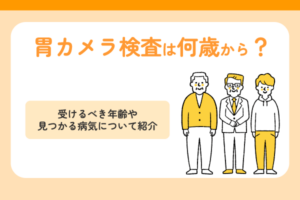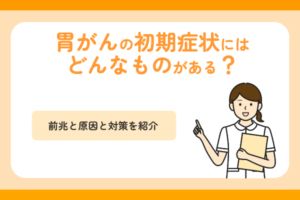「胃ポリープができやすい人に当てはまっているようで、将来がんにならないかすごく不安だ」という人は少なくありません。
胃ポリープができやすい人の特徴は、以下のように先天的、後天的な要因に分けることができます。
| 胃ポリープができやすくなる要因 | |
|---|---|
| 先天的 | 性別、遺伝 |
| 後天的 | 細菌感染、生活習慣、加齢 |
先天的なもの以外では、胃ポリープが出来やすい人には共通する特徴があり、生活習慣や体質と深く関係しています。
この記事では胃ポリープができやすい人の特徴や理由、そして対策について紹介します。
- 胃ポリープができやすい人の特徴
- 胃ポリープの基礎知識
- 胃ポリープの診断や治療・予防方法
胃ポリープが出来やすい人の特徴
胃ポリープが出来やすい人には、前述したようにいくつかの共通した特徴があります。
性別や遺伝といった先天的なものや、年齢、生活習慣、細菌感染と言った後天的なものまで、胃ポリープができやすい要因というのは多岐にわたります。
ここでは、遺伝的な要素を除き、感染症や加齢、性別、生活習慣などに焦点を当て、それぞれ詳しく解説していきます。
ピロリ菌に感染していると胃ポリープはできやすい
ピロリ菌に感染していると胃の粘膜に慢性的な炎症が起こりやすくなり、胃ポリープの発生リスクが高まります。
ピロリ菌とは、正式名称を「ヘリコバクター・ピロリ」といい、胃ポリープ以外にも、胃炎や胃潰瘍といった様々な症状の要因となることが多い細菌です。
特徴としては、移動の際、鞭毛を旋回させて胃内を移動するため、その影響で胃粘膜にダメージを与えることや、胃酸から身を守るためにアルカリ性であるアンモニアを生成して胃粘膜を刺激して炎症を促すといった問題を引き起こします。
そんなピロリ菌の感染経路は断定はされていないものの、主に幼児期の経口感染だと考えられています。
また、幼児期に感染するというものが多い反面、成人してから感染するといったケースは極めて稀です。
成人になってから感染するケースとしては、衛生環境が悪いところでの飲水が主な要因としてあげられますが、日本では上下水道が整備されているところがほとんどのため、海外旅行で水道整備がされていない地域にいかない限り、感染のリスクはないでしょう。
しかし、60代以降の高齢者の場合、まだ日本で上下水道が整備されていない時代に感染し、その子供が経口感染で感染するという経路もあるので注意しましょう。
高齢者であれば胃ポリープはできやすくなる
高齢者になった場合、胃ポリープは発生しやすくなるといわれています。
具体的な年齢を上げると、だいたい50歳後半から60歳以降が当てはまります。
これは、加齢に伴い代謝が悪くなり、胃の粘膜の再生能力が低下して組織の変性が進みやすくなるのが原因です。
そのため、60歳以上では胃底腺ポリープや過形成性ポリープの発生リスクが上昇します。
また、代謝や免疫の低下に伴い発生した疾患の治療として薬を長期服用することで、胃腸の環境に何らかの影響を与えてポリープができてしまうということもあります。
これらの要素が複合的に影響し、ポリープ形成が若者よりも促進されやすい環境になっているため、高齢者は胃ポリープ発生のリスクが高いです。
女性の方が胃ポリープはできやすい
女性の場合、男性に比べると胃ポリープはできやすいという傾向があります。
その理由としては、以下のものが挙げられます。
| 要因 | 影響 |
|---|---|
| ホルモンバランス | 胃粘膜の細胞増殖促進 |
| 鉄欠乏性貧血 | 粘膜の脆弱化 |
| 胃酸分泌の違い | 胃の防御機能に影響 |
これは女性ホルモン(エストロゲン)が胃粘膜の細胞増殖に影響を与えるためと考えられています。
また、女性は鉄欠乏性貧血が起こりやすく、胃粘膜の異常を誘発することもあります。
特に更年期以降の女性では、ホルモンバランスの変化により胃粘膜の変性が進みやすくなることが知られており、定期的なチェックが推奨されています。
しかし、これら要因で発生するポリープは「胃底腺ポリープ」と呼ばれるものが主であり、がん化したり体調に悪影響を及ぼしたりするリスクは限りなく低い良性のものがほとんどです。
そのため、基本的に摘出する必要もなく、放置しても定期的な健康診断で経過観察さえすれば、命に関わるリスクはほぼ0といってもよいでしょう。
というのも、胃がんは病気の進行が極めて遅く、初期段階は年単位で進行するため、1年に1回健康診断でチェックすれば、症状が進行する前に極めて低いリスクで発見・治療が行えるからです。
生活習慣で胃ポリープの出来やすさは変わる
後天的に胃ポリープの発生率が高くなる要因としては、生活習慣が関わっていることが多いです
日常生活の習慣は、蓄積することで胃の健康に直接影響を与えます。
以下に胃ポリープ発生リスクを高める生活習慣をまとめました。
| 生活習慣 | リスク |
|---|---|
| 喫煙 | 胃粘膜の血流を悪化させ、炎症を引き起こす |
| 過度の飲酒 | 胃酸の分泌を促進し、粘膜を刺激する |
| 高脂肪・高塩分食 | 胃に負担をかけ、粘膜の損傷を招く |
| 不規則な食生活 | 胃酸の過剰分泌や胃の運動異常を引き起こす |
| ストレス過多 | 胃のリズムを乱し、消化機能を低下させる |
これら要因は厚生労働省の「生活習慣病」の項目でも記載されており、慢性影響による臓器障害として警告しています。
また、これら生活習慣は胃ポリープ以外にも様々な疾患の要因となるため、これら5つの項目で当てはまるものが複数ある場合、改善は必須です。
なお、改善が必要なのはこれらを日常的に行っている場合であり、月に一度程度の過食や飲酒程度なら受ける影響も極めて少ないでしょう。
胃ポリープとは?その種類と特徴
胃ポリープと一口に言ってもその種類は様々です。
胃ポリープとは、胃の粘膜にできる隆起性病変の総称であり、種類によって性質やがん化リスクが異なるため、それぞれの特徴を正しく理解することが大切です。
そんな胃ポリープはおもに以下の3種類に分けられます。
| 種類 | 特徴 | がん化するリスク |
|---|---|---|
| 胃底腺ポリープ | 胃の上部にできる小さなポリープ。 | 極めて低い |
| 過形成性ポリープ | 胃炎やピロリ菌感染により発生。出血しやすい。 | 稀にリスクあり |
| 腺腫性ポリープ | 胃粘膜の腺細胞が異常増殖したポリープ | 要注意 |
ここでは、これら3つのポリープについて紹介しましょう。
胃底腺ポリープ
胃底腺ポリープは、胃の上部(胃底部)にできる小さな良性のポリープです。
ピロリ菌に感染していない人に多く見られ、ほとんどが無症状で経過します。
がん化のリスクは極めて低いため、定期的な経過観察で十分なケースがほとんどです。
ただし、大きさが増大する場合や出血リスクがある場合には切除が検討されます。
欧米の研究では、胃底腺ポリープの約90%以上が良性であることが示されており、比較的安心して経過を見守ることが可能です。
過形成性ポリープ
過形成性ポリープは、慢性胃炎やピロリ菌感染による胃粘膜の過剰な再生反応によって形成されます。
最も多くみられるタイプで、胃の内容物が触れることで出血を起こすことがあるため、血便の原因になることもあります。
この場合、便の色は黒い便になることが多いです。
がん化リスクは低いですが、サイズが大きい場合や急速に増大する場合には切除が推奨されます。
具体的には、がん化のリスクについては10mm以上のサイズのポリープでもがん発生確率はわずか2%程度のため、不安な場合は摘出してもらうか、あるいは経過観察で定期的な検査で経過観察するのが主流です。
2cmを超えるサイズになっている場合は、慎重な対応が求められますが、不安な場合は内視鏡手術で摘出しましょう。
日本消化器内視鏡学会による報告では、ピロリ菌の除去を行えば、8割方ポリープの縮小あるいは消滅が確認されています。
腺腫性ポリープ
腺腫性ポリープは、胃粘膜の腺細胞が異常増殖してできるポリープで、がん化リスクが高いとされています。
特徴としては、見た目は白っぽく、隆起も平坦なものが多いです。
この時点ではがん化していないため影響は少ないですが、進行すると計上がいびつな形になり、サイズも2cm以上に大きくなります。
腺腫性ポリープも基本は無害な良性のものが多いですが、10mm以上の大きなものでは、早期胃がんとの鑑別が重要になります。
発見された場合は、通常内視鏡的切除が行われ、病理検査で良性・悪性の判別が行われます。
日本消化器内視鏡学会によると、腺腫性ポリープの約30〜40%が将来的にがん化する可能性があるため、早期切除が強く推奨されています。
胃ポリープの検査と診断方法
胃ポリープの有無や性質を正確に把握するためには、適切な検査が不可欠です。
胃腸内の異常を調べる検査としては、健康診断で行われる便潜血検査が一般的ですが、より詳しくポリープの有無を調べる場合は「バリウム検査」と「内視鏡検査」のどちらかを行うことになります。
ここでは、バリウム検査と内視鏡検査の2つについて紹介します。
バリウム検査
バリウム検査(胃透視検査)は、バリウム剤を飲んでX線撮影を行い、胃の形態異常やポリープをチェックする検査です。
具体的な検査方法は、バリウム剤を飲んだ後、発泡剤を飲むことで胃を膨らまし、患者の身体を上下左右に動かすことでバリウム剤を胃の中に満遍なく塗布させ、X線を用いて内部を撮影します。
メリットは、比較的簡便に広範囲をスクリーニングできる点であり、検査自体も10分程度で終わることが多いです。
しかし、小さなポリープや粘膜の微細な変化を捉えるのは難しく、異常が見つかった場合には精密検査(内視鏡)が必要となります。
また、患者によっては発泡剤を服用したあとげっぷをしたらもう一度飲み直さなければならなかったり、検査後にバリウム剤を排出するため下剤の服用が必要になったりと若干負担がかかるという点もデメリットと言えるでしょう。
国立がん研究センターの資料によると、バリウム検査単独での診断精度は内視鏡に比べてやや劣るとされており、確実な診断には内視鏡併用が推奨されています。
内視鏡検査
内視鏡検査(胃カメラ)は、口または鼻からスコープを挿入し、胃内部を直接観察する検査です。
バリウム検査はX線で胃の内部をスクリーニングするという手法ですが、こちらは直接胃の内部を見るという方法のため、ポリープの形態、大きさ、色調を詳細に把握でき、必要に応じて組織を採取(生検)して病理検査を行うことが可能です。
診断精度が高く、小さな病変も見逃さないため、現在では胃ポリープ診断のスタンダードとなっています。
日本消化器内視鏡学会ガイドラインでは、内視鏡検査を年1回程度受けることが、胃疾患の早期発見において有効とされています。
しかし、こちらも使用時に喉に触れることでえづきやすくなったり、人によっては痛みを感じたりと、バリウム検査とは異なったデメリットがあるので、人によっては忌避する事が少なくありません。
そのため、クリニックによっては麻酔を用いて患者の痛みを麻痺させてから行われることが多いです。
胃ポリープの予防と生活習慣の改善
胃ポリープは、ピロリ菌の除去や生活習慣の見直しで、改善と予防が期待できます。
上述したように、生活習慣は後天的に胃ポリープが発生する要因として、成人でも発生リスクが高まる要素です。
また、胃ポリープ以外にも様々な疾患を招く要因でもあるので、健康維持のため生活習慣の見直しは欠かせません。
ここでは、そんな生活習慣の改善について紹介します。
ピロリ菌の検査と除菌
胃ポリープの原因がピロリ菌なのであれば、ピロリ菌を除去すれば胃ポリープのリスクを大幅に下げられます。
ピロリ菌の有無を調べる検査は、内視鏡検査、血液検査、呼気テストなど複数ありますが、基本的に内視鏡検査で行うケースが多いです。
感染が確認された場合は、抗生物質を用いた除菌治療が推奨されます。
除菌によって胃炎の進行を防ぎ、胃ポリープの発生リスクを大幅に減少させることが可能です。
日本ヘリコバクター学会のガイドラインでも、除菌治療による胃ポリープ予防効果が強調されており、除菌治療後には胃粘膜の炎症が改善し、新たなポリープ形成率が著しく低下することが報告されています。
食生活の改善
生活習慣の多くは、食生活の改善で解消できます。
具体的には、以下の3つを行うことで、胃腸の環境は大きく改善されやすくなります。
- 野菜や果物を中心に摂取
- 高脂肪・高塩分の食品を控える
- 発酵食品(ヨーグルト、味噌など)を取り入れる
これらを意識することで、胃粘膜を健やかに保ち、ポリープ形成を抑制できます。
発酵食品や野菜・果物類は、腸内環境を整えるのに必須な善玉菌の栄養となるからです。
また、ビタミンCや食物繊維が豊富な食品は、胃の粘膜防御機能を高める効果があるとされています。
腸内環境を整えることで免疫力も向上し、胃全体の健康維持にもつながるのもメリットといえるでしょう。
アルコールと喫煙の制限
禁酒・禁煙は胃の負担を大幅に減らします。
アルコールとタバコは胃粘膜への強い刺激物であり、習慣的な飲酒や喫煙を控えることで、胃粘膜の炎症リスクを低下させ、ポリープやその他の胃疾患の予防につながります。
国立がん研究センターのデータによると、喫煙者は非喫煙者に比べて胃がんリスクが約2倍高いとされており、禁煙は胃ポリープ予防にも有効な手段といえます。
まとめ
この記事では、胃ポリープができやすい人の特徴や改善・予防方法などを紹介しました。
胃ポリープは多くの場合良性ですが、種類や大きさによってはがん化リスクがあるため注意が必要です。
ピロリ菌感染や加齢、女性ホルモン、生活習慣などが発生リスクに関係しており、定期的な検査と生活習慣の改善が重要です。
特に、ピロリ菌除菌やバランスの取れた食生活、禁煙・節酒の実践により、胃の健康を長期的に守ることができます。
自分自身のリスク要因を正しく理解し、早期発見・早期対策を心がけましょう。健康な胃を保つことが、将来の病気予防にも直結します。
将来のリスクを考え、胃の健康を適度に維持するよう努めましょう。