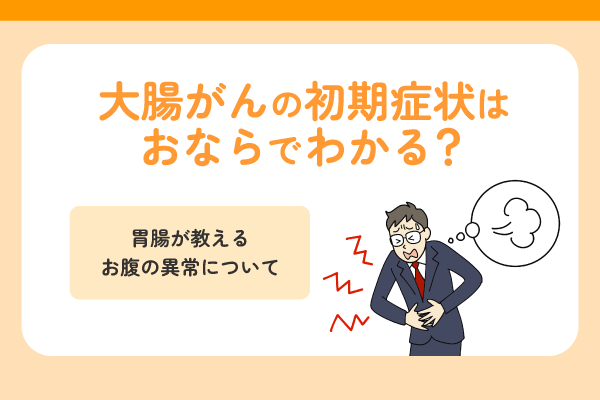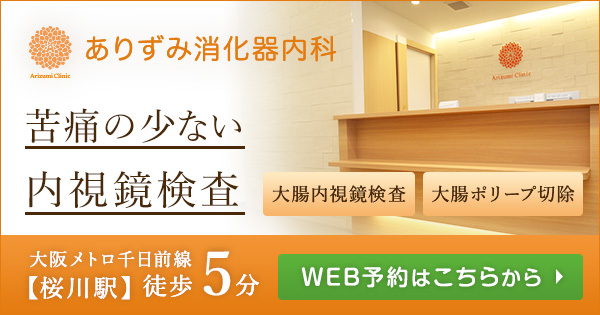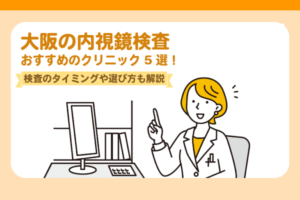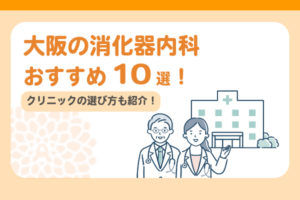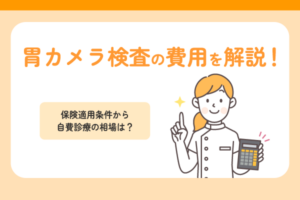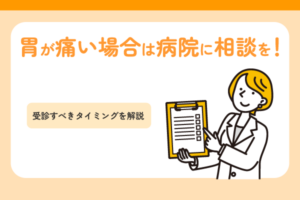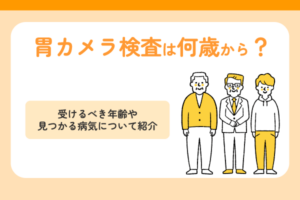「大腸がんの初期症状はおならでわかるって本当?」と、健康に気を使う人ほどおならに変化があると不安になりやすいものです。
結論からいえば、おならに変化があったとしても、大腸がんになっている可能性はほぼ0に近いといってよいでしょう。
しかし、おならの変化は胃腸に異常が出ている可能性があるため、長期間おならの異常が改善されない場合は病気を疑ったほうが良いかもしれません。
場合によっては、何らかの胃腸の異常から大腸がんになる可能性があるからです。
の記事では、おならと大腸がんの関係、胃腸の異常サイン、早期診断の重要性を詳しく解説します。
お腹の不調が気になる人は、ぜひご一読ください。
- おならと大腸がんの関係
- おならでわかる体調異常
- おならの異常の解決方法
おならは大腸がんの初期症状ではない
上述したように、おならの臭いの変化は大腸がんの初期症状として当てはまることはほぼありません。
しかし、おならの臭いの変化の原因が、巡り巡って大腸がんに行き着く可能性はあります。
ここでは、おならと大腸がんの関係について解説しましょう。
大腸がんの初期症状に自覚症状はほとんどなし
大腸がんは初期段階では自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行する特徴があります。
症状が出始めるのはある程度進行してからであり、初期段階で見つかるケースの多くは便潜血検査や内視鏡検査の定期的な検査です。
初期症状がない理由は、腸内にがんがあっても痛みや違和感が出にくい構造だからです。
大腸がんとは、大腸内にできた腫瘍が肥大化する病気であり、その腫瘍が腸内を圧迫したり、腸管の通りを妨げたりすることで症状が発生します。
よって、ごく小さな腫瘍のままだと症状は全く現れません。
そのため、「おならが増えたから大腸がんかも」と心配するよりも、定期的な検査を受けることが重要です。
おならの変化=胃腸に問題が起きている可能性はある
上述したように、おならの臭いは大腸がんの初期症状である原因は限りなく低いです。
しかし、腸内の病気は大腸がんだけではなく、他の病気が引き起こしている可能性があります。
おならの回数や臭いの変化は胃腸の消化機能に問題があるサインかもしれません。
例えば、腸内細菌バランスの乱れや食物繊維不足、過剰な脂質摂取などが原因として考えられます。
また、これらが原因で以下のような病気を発症している場合もあります。
| 病気名 | 特徴・症状 |
|---|---|
| 過敏性腸症候群(IBS) | ガスが溜まりやすく、おならが頻繁に出る。腹痛や便秘・下痢を繰り返す。 |
| 小腸内細菌異常増殖症(SIBO) | 腸内で異常発酵が起き、強い臭いのおならや腹部膨満感が出る。 |
| 潰瘍性大腸炎 | 血便や下痢を伴い、おならが増えることもある。慢性的な炎症が特徴。 |
これらの病気は、大腸の病気のほんの一部です。
また、これらが悪化した場合、腸内環境がより悪化し、大腸がんのリスクが高まってしまいます。
そのため、おならの臭いは大腸がんの初期症状ではありませんが、別の病気が原因で大腸がんになる可能性があるということは覚えておきましょう。
おならが教える胃腸の異常
おならの変化は、胃腸が異常を発しているサインでもあります。
回数の増加や臭いの強さ、腹痛の有無など、さまざまなサインを見逃さないことが、健康維持、ひいてはがんの予防につながるといえるでしょう。
ここでは、おならを通じてわかる胃腸の異常の具体的な特徴を解説します。
おならの回数が増えている
おならの回数が増える理由は、食事や生活習慣、腸内環境の変化などが当てはまります。
おならは、腸内に空気もしくはガスが貯まることで発生する生理現象です。
空気を吸っていればお腹に空気は溜まりやすくなりますし、食事内容によっては食材を分解する過程でガスが発生する可能性があります。
おならが増える要因として考えられるのは、主に以下の要因が影響していることが考えられます。
| 原因 | ガスが増える理由 |
|---|---|
| 食物繊維の摂取増加 | 食物繊維は腸内細菌によって発酵され、その際に大量のガスが生成される。 |
| 炭酸飲料やガムの摂取 | 飲み込む空気の量が増え、腸内に余分なガスが溜まりやすくなる。 |
| 早食いや空気の飲み込み | 食事中に空気を飲み込みやすくなり、その空気が腸内でガスとして排出される。 |
| 腸内細菌バランスの乱れ | 発酵や腐敗のバランスが崩れ、通常より多くのガスが発生する。 |
回数の増加は、必ずしも深刻な病気のサインではありませんが、腸が過剰にガスを生成している状態を示しています。
放置すると腹部の張りや不快感が続き、生活の質が低下する恐れがあります。
ガスが溜まりやすい食材や習慣を見直し、改善が見られない場合は専門医の相談を検討しましょう。
おならの臭いが変化している
おならの臭いが以前より強くなった場合、腸内でタンパク質や脂質の分解が進んでいることが原因と考えられます。
特に、腐敗を伴う悪臭は腸内のバランスが乱れているサインです。
腸内に住んでいる常在菌は善玉菌と悪玉菌と日和見菌に分類され、タンパク質や脂質を分解するのは悪玉菌です。
つまり、タンパク質の分解が進んでいるというのは悪玉菌が活発であり、善玉菌とのバランスが崩れているということでもあります。
臭いとその原因に関してまとめましたので、自分のおならの臭いがどれに当てはまるか確認してみましょう。
| 臭いの種類 | 主な原因 |
|---|---|
| 腐った卵のような臭い | タンパク質の過剰摂取、腸内腐敗 |
| 酸っぱい臭い | 消化不良、乳製品や糖質の過剰摂取 |
| 異常に強い悪臭 | 腸内細菌バランスの崩れ、炎症性疾患の可能性 |
臭いの変化は一時的な食事の影響であることも多いですが、長期的に続く場合は腸疾患の兆候である場合もあります。
早めに食事内容を見直し、症状が続くようであれば専門医に相談しましょう。
おなら以外にも腹痛が頻発している
おならと共に腹痛が頻繁に起こる場合、腸の機能や構造に異常が生じている可能性があります。
腹痛が発生する主な理由は、腸内ガスの過剰な溜まり、腸の過剰な収縮、炎症の進行などが関係しています。
具体的には、以下のような疾患が背景にあるかもしれません。
| 病気名 | 痛みが発生する理由 |
|---|---|
| 過敏性腸症候群(IBS) | 腸が過敏に反応し、通常より強い収縮やけいれんが起きる。 |
| 炎症性腸疾患(IBD) | 腸内に慢性的な炎症が発生し、組織が傷ついて痛みが出る。 |
| 腸閉塞 | ガスや便が腸内に詰まり、腸が拡張して強い圧迫感や痛みを感じる。 |
腸内ガスが過剰に溜まると腸壁が引き伸ばされ、神経が刺激されて痛みが発生します。
また、腸の動きが乱れるとガスの排出がうまくいかず、さらに痛みが強まるかもしれません。
腸の異常は早期対応が鍵であり、原因を特定して適切な治療を受けることで症状の改善が期待できます。
おならの異常が続くなら消化器内科で診察を受けよう
おならの頻発や臭いの悪化、腹痛などの症状が継続するのであれば、消化器内科の受診をおすすめします。
おならの変化や腹痛は、一過性のものもあり、一晩寝たら治っているケースが多いです。
しかし、一過性ではなく、一週間以上症状が続く場合、何らかの症状を発症している可能性があり、生活習慣だけでは改善が難しいケースがあります。
特に、腸内環境の乱れや腸疾患の早期発見・早期治療は非常に重要です。
ここでは、医療機関を受診する必要性と、検査や予防の重要性について詳しく解説します。
胃腸の異常は初期段階で対策すれば痛む前に対処しやすい
胃腸の異常は初期段階で気づき、対策を講じることで症状の悪化を防げます。
胃腸の症状は、基本的に自覚症状が出始めるのが遅いです。
また、軽い腹痛や膨満感程度であり、深刻な痛みではないということから放置したり、あるいは市販の胃薬を買って治そうとする人は少なくありません。
たしかに、一過性の症状であれば市販の胃薬で十分な効果が期待できますが、胃腸炎や胃潰瘍の場合、市販薬だけで直そうとするのは非常に時間がかかりますし、薬の費用が治療費より高くつくこともあります。
何より、放置すればその分症状が悪化し、より腹痛が激しくなることも考えられます。
そのため、軽い腹痛でも一週間も続くのであれば、早めに病院で診断を受けて、適切な対応をしましょう。
診断の結果、生活習慣の乱れによる一過性のものである場合、再発防止のために普段の食生活や運動習慣の見直しを行う必要があります。
腸内環境の改善や食生活の見直しは、初期段階では特に効果的です。
例えば、発酵食品や食物繊維を積極的に取り入れることで、腸内細菌のバランスを整えやすくなります。
また、40過ぎた場合は生活習慣の見直しに加え、定期的な健康診断をおすすめします。
定期的な検査で大腸がんのリスクは大幅に減りやすくなる
大腸の症状悪化を防ぐ手段で最も効果が期待できるのが、年に一度の定期検診です。
特に、大腸がんは年に1回定期検査を受けているのといないのとでは大きく違います。
大腸がんは早期に発見すれば高い確率で治療可能ですが、症状が出るころには進行していることが多いです。
しかし、大腸がんの初期の進行速度は極めて遅く、数年腫瘍を放置していることで、次のステージに進みます。
そのため、1年に1回検査をして大腸の健康チェックを行えば、初期段階での大腸がんを発見しやすくなるということです。
国立研究開発法人国立がん研究センターによると、初期段階で大腸がんを発見できた場合、診断から5年後の生存割合は90%以上ですが、ステージ2に進んだ場合、生存率は80%まで下落します。
また、40代になるとがんの発症率が上昇するという報告もされているため、40歳を過ぎたら定期的に便潜血検査や大腸内視鏡検査を受けることが推奨されています。
特に以下のような人は注意が必要です。
- 家族に大腸がんの患者がいる
- 肥満や運動不足が続いている
- 肉類中心の食事が多い
検査によって無症状のうちにがんを発見できれば、治療の負担を大幅に軽減できます。
予防としての検査は将来の安心につながるため、積極的にスケジュールを立てることが大切です。
健康診断の機会や自治体のサービスを活用し、胃腸の状態を定期的にチェックしましょう。
まとめ
この記事では、おならと大腸がんの初期症状の関連性について紹介しました。
基本的に、おならの臭いが変わったり、回数が増えた程度では大腸がんと断定する必要はほぼありません。
しかし、おならの回数や臭いの変化が長期間続く場合には、腸疾患のサインである可能性があります。
そして、腸疾患によって大腸がんにつながるリスクはあるため、大腸がんと関係していなくても、注意は必要です。
胃腸の疾患は早期発見・早期治療ができれば重症化を防ぐことが可能です。
定期的な検査を受ける習慣を持ち、日々の食生活や排便状態に注意を払うことが、将来の健康につながります。
体からの小さなサインを見逃さず、自分自身の健康を守るための行動を意識することが何より大切です。