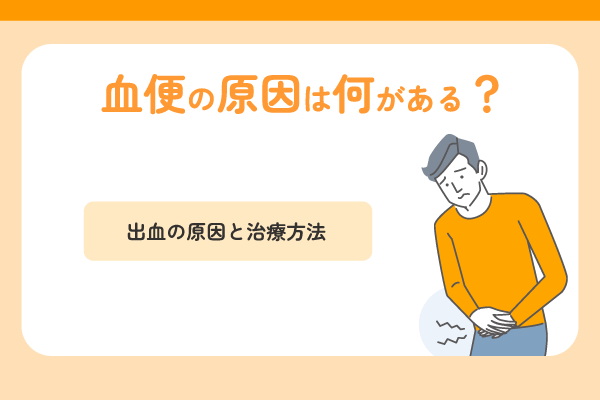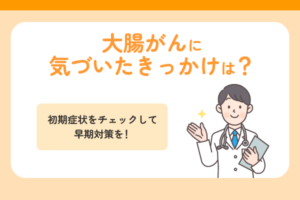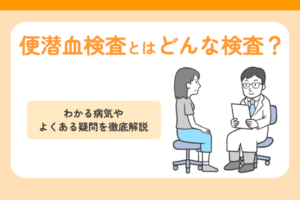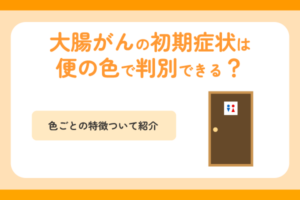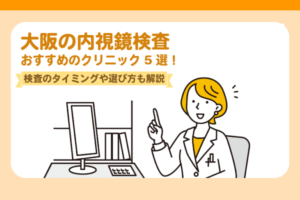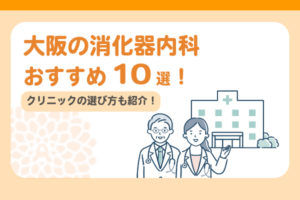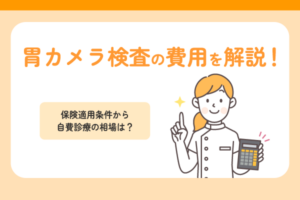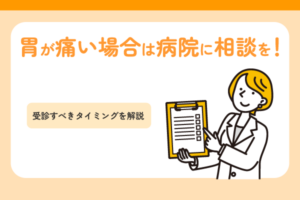「血便が出たが、原因はなんだろう?」
「血便が出たら大腸がんかもしれないというのは本当だろうか?」
突然、血便が出てしまい不安になっている方も多いかと思います。
血便を引き起こす原因として、以下の6点が挙げられます。
- 痔
- 食あたり
- 胃潰瘍
- 大腸炎
- 大腸ポリープ
- がん
色や形状によって痔・胃がん・大腸がんなど、様々な症状の可能性があるので血便が続く場合は病院での診察を推奨します。
ここでは、血便でわかる原因や疾患、疾患の治療方法などを解説します。
そもそも血便とは?
血便とは、便に血液が混じっている状態のことを指します。
血便には、便全体が赤く染まるものや、血が付着しているものなどさまざまなタイプがあり、その原因も多岐にわたります。
血便が見られた場合、一時的なものであれば心配ないケースもありますが、大腸がんや潰瘍性大腸炎などの重篤な病気が隠れていることもあります。
そのため、血便が頻繁に見られる場合や、腹痛や体調不良を伴う場合には、早めに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。
血便と判断する基準
血便を判断する基準は、以下の3点が挙げられます。
- 便表面に鮮紅色の血液が付着している
- 便全体が赤黒く変色している
- トイレットペーパーに血が付着する
判断基準として注意すべき点は、出血量と色の関係性です。痔では少量の鮮血が便表面に付着するのに対し、大腸憩室出血では多量の暗赤色便が突然出現します。
ただし、自己判断は危険で、鮮血便でも直腸がんの可能性があるため、必ず専門医の診察が必要です。
便の色が正常でも、下痢や腹痛を伴う場合、細菌性腸炎などによる微量出血が疑われるため、早期の検査が求められます。
血便を引き起こす原因
血便を引き起こす原因として挙げられるのは、主に以下の6点です。
- 痔
- 食あたり
- 胃潰瘍
- 大腸炎
- 大腸ポリープ
- がん
痔や食あたりなど、軽症で済む場合もありますが、がんなど命に関わる病気が関係している場合もございます。
それぞれの症状について解説しているので、参考にして病院の受診を検討してください。
痔
痔とは、おしりから血が出る疾患の総称です。
痔といってもその種類は3種類あり、以下の3タイプに分けられます。
- 痔核:肛門周辺の毛細血管が静脈瘤となりコブ状になったもの。別名いぼ痔
- 裂肛:肛門周辺の皮膚が裂けている状態のもの。別名切れ痔
- 痔瘻:肛門周辺に膿が溜まってしまった状態のもの。
これらの痔で血便になる原因は、いきんだ際の圧力で血管が膨張したり、肛門の粘膜が傷ついたりすることが挙げられます。
軽度の痔であれば、食物繊維の摂取や水分補給、適度な運動で改善が期待できることも多いですが、痛みや出血が続く場合には薬物療法や手術が必要です。
特に痔瘻は症状が悪化すると直腸と皮膚の間に隙間ができてしまい、便に含まれた細菌が血に入り込んでしまい、敗血症の元となるリスクがあります。
そのため、痔の症状が続く場合は自己判断で放置せずに早期の医療機関での診断を受け、適切な治療を行うことが大切です。
食あたり
食あたりによって腸内が荒れてしまい、血便が引き起こされることもあります。
症状:激しい下痢、嘔吐、腹痛
原因:サルモネラ菌、大腸菌、ノロウイルスなどの食中毒菌
対処法:軽度の場合水分補給、重度の場合は病院での抗生物質投与
食あたりは、主に細菌感染による消化器官の炎症が起きる症状です。
汚染された食べ物や飲み物に含まれる病原菌が体内で感染を引き起こし、消化器官の炎症を引き起こします。
食あたりは重度の場合下痢や嘔吐によって脱水症状を起こしてしまい、命の危険もある状態です。
軽度の場合でも病院に行き、正しい治療を受けましょう。
胃潰瘍
胃潰瘍が進行すると胃の内部で出血が起き、タール便の原因となります。
症状: 腹痛、胸やけ、胃もたれ
原因:ピロリ菌感染、非ステロイド性抗炎症薬の過剰使用、ストレスなど
対処法:胃酸を抑える薬物療法、ピロリ菌の除去治療など
胃潰瘍は、胃の粘膜に保護されている筋層(胃を動かすための筋肉のある部位)まで炎症し、傷ついている状態の症状です。
胃潰瘍の場合、痛みを感じるケースはほとんどありませんが、胸焼けや胃もたれによる吐き気を訴えることが多いです。
自然治癒するケースもありますが、放置すると胃がんの原因にもなるので早期治療が好ましいです。
よって、早めに病院で正しい治療を受けて治しましょう。
大腸炎
大腸炎とは、大腸が何らかの原因で炎症を起こしている症状で、胃潰瘍と同じく腸壁の炎症による出血が原因で血便が発生します。
症状:下痢、腹痛、発熱
原因:細菌感染、自己免疫疾患、ストレスなど
対処法:抗生剤治療、生活習慣の見直しなど
胃潰瘍とは異なり、大腸炎はピロリ菌ではなく免疫の異常が原因とされており、長期間の治療が必要な病気です。
目や関節にも合併症が出る恐れがあり、大腸がんのリスクも高くなるため、腸内環境は良好に保ちましょう。
大腸ポリープ
大腸ポリープとは、大腸内に発生する腫瘍のことで、良性の腫瘍を大腸ポリープと位置づけられています。
大腸ポリープは肛門の近くにできると、便とこすれて血便が引き起こされる可能性があります。
ですが、ポリープが原因の場合は目に見えるほどの出血はほとんどありません。
症状: 腸閉塞、悪性腫瘍(がん)化
原因: 食習慣を中心とした生活習慣の改善
対処法: 消化器外科による手術
大腸がん
血便は大腸がんが原因となっている可能性もあります。
大腸がんが原因となる理由はポリープと同じく、便が兆を通る際に擦れてしまうためです。
症状: 食欲不振、倦怠感背中や胸の痛み、胃腸の機能不全など
原因: 塩分過多の食生活、遺伝など
対処法:消化器外科による手術
初期段階では進行速度は遅いですが、放置すると進行速度が早くなり、最終的に全身に転移し、死に至る可能性があります。
症状に心当たりがある場合は、放置せずに必ず病院を受診して、検査を受けるようにしましょう。
原因によって血便の色が異なる
血便は原因によって色が異なります。
原因とそれぞれの血便の色は以下のとおりです。
| 原因 | 血便の色 | 出血箇所 |
|---|---|---|
| 痔・裂肛 | 鮮血便 | 直腸及び肛門付近 |
| 大腸炎・大腸がん | 暗赤色便 | 腸の中部 |
| 胃潰瘍・胃炎・胃がん | タール便 | 胃や十二指腸など上部消化管 |
なぜ原因によって色が変化するのかというと、血液に含まれているヘモグロビンが影響しています。
ヘモグロビンには鉄分が含まれており、酸化することで黒く変色します。
消化管の上部で出血している場合、長時間血液が付着した状態で排出されるため、ヘモグロビンの酸化も進み、コールタールのように黒い便になります。
腸の中部で出血した場合の便が暗赤褐色なのは、排出される便に付着した血液が酸化した時間がタール便より短いからです。
肛門部や直腸部などで出血している場合は血液の付着から便としての排出まで時間が短いため、鮮やかな赤色の血便になります。
貧血の治療で鉄分のサプリを使用している場合、吸収されなかった鉄分が付着して便が黒くなるケースがあります。
また、色が黒い食べ物やワインのポリフェノールも、同様に便を黒くする場合があります。
そのため、これらを服用、あるいは飲食している場合は、後日これらを使用していないタイミングで確認しましょう 。
血便が出てしまった際の対処法
血便が出ると、パニックになり、どうすればよいのかわからなくなる方も多いでしょう。
血便が出てしまった際の対処法は、以下の2点です。
- すぐに食生活を見直す
- 消化器内科や肛門科を受診する
すぐに食生活を見直す
血便が出た場合、まずは食生活を見直すことが重要です。
刺激の強い食べ物や脂っこい料理、アルコールの過剰摂取は腸内環境を悪化させ、出血を引き起こす可能性があります。
特に、辛い食べ物やカフェインを多く含む飲料は、消化器官への負担を増やすため注意が必要です。
代わりに、食物繊維が豊富な野菜や果物、発酵食品を積極的に摂取し、腸内の善玉菌を増やすことで便通を改善できます。また、水分をしっかりと補給し、便を柔らかくすることも大切です。
便秘や下痢が続くと肛門への負担が増し、血便の原因となるため、バランスの取れた食事を心がけることが血便の予防と改善につながります。
消化器内科や肛門科を受診する
血便が見られた際は、消化器内科や肛門科を受診し、適切な診察を受けることが大切です。
血便の原因は痔や腸炎など比較的軽度なものから、大腸がんや潰瘍性大腸炎などの重篤な病気まで多岐にわたります。
特に、血便が繰り返し起こる場合や、腹痛や体調不良を伴う場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
診察では、問診のほかに便潜血検査や大腸内視鏡検査を行い、出血の原因を特定することが一般的です。
早期発見・早期治療を行うことで、症状の悪化を防ぎ、健康を維持することができます。
血便が続く場合は自己判断せず、専門医の診断を受けるようにしましょう。
すぐに検査が必要な血便の種類
血便が確認された場合、放置せず早めに医療機関で検査を受けることが重要です。
特に以下のような症状がある場合、早急な検査が必要です。
- タール便
- 大量の鮮血便
- 持続する血便
胃がんの可能性もあるため、タール便は確認次第病院で検査を受けて胃腸内の検査をしたほうが良いでしょう。
鮮血便はがんのリスクは低いですが、血液量が多い場合出血箇所が複数、あるいは裂傷箇所が大きい可能性があるので、別の大きな問題が生じている可能性があります。
タール便じゃなくても長期間にわたって血便が見られる場合、大腸がんや炎症性疾患の疑いがあるため、精密検査をして確認したほうが良いでしょう。
血便を予防するポイント
血便が出る前に予防するポイントは以下の通りです。
- 定期的に内視鏡検査を受ける
- 便秘が続かないように注意する
- ピロリ菌の除去治療を受ける
それぞれ具体的に解説していますので、大事になる前に予防できるよう、参考にしてください。
定期的に内視鏡検査を受ける
定期的に内視鏡検査を受けることが血便の一番の予防です。
血便の原因となる疾患は、早期発見と治療が重要です。
特に40歳以上の方や血便の症状がある方は、定期的な内視鏡検査検査を受けることで、がんやポリープといった病気の早期発見が可能になります。
胃がんや大腸がんは初期段階では進行が遅いため、1年に1回の定期検診を受けることで、初期の悪性腫瘍を発見・摘出できる可能性が高まります。
また、内視鏡検査では悪性腫瘍の摘出が行えるものもあるので、切開せずに摘出手術を行ない、患者の負担を減らせます。
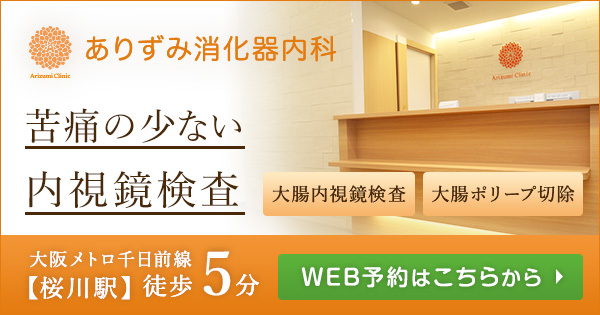
内視鏡検査はありずみ消化器内科へ
便秘が続かないように注意する
便秘が続くと硬い便が肛門や直腸を傷つけ、出血の原因となるため、便秘を防ぐことが重要です。
また、排便時の強いいきみは肛門に負担をかけ、痔を悪化させることもあります。
便秘を防ぐためには、食物繊維が豊富な野菜や果物、発酵食品を積極的に摂取し、腸内環境を整えることが大切です。
加えて、水分をしっかりと補給し、適度な運動を取り入れることで腸の動きを活性化させることができます。
特に、朝起きたらコップ一杯の水を飲むことで腸を刺激し、自然な排便を促すことができます。
便秘を放置すると慢性的な腸のトラブルにつながる可能性があるため、日頃から排便リズムを整えることを意識しましょう。
ピロリ菌の除去治療を受ける
血便の原因として、ピロリ菌が関与していることがあります。
ピロリ菌は胃の粘膜に感染し、慢性的な炎症を引き起こすことで胃潰瘍や十二指腸潰瘍を発症させる可能性があります。
これらの疾患が進行すると消化管からの出血が発生し、血便の原因となることがあります。
そのため、ピロリ菌の感染が疑われる場合は、医療機関で検査を受け、必要に応じて除菌治療を行うことが推奨されます。
除菌治療では、抗生物質と胃酸を抑える薬を服用することで、ピロリ菌を効果的に除去できます。
特に、過去に胃潰瘍を患ったことがある人や、家族に胃がんの既往歴がある場合は、早めの検査と治療を検討するとよいでしょう。
まとめ
この記事では、血便の原因と種類、そして種類別の治療方法について紹介しました。
血便は発生すると恐ろしく感じますが、実際には自分の胃腸の状態をわかりやすく確認できる方法でもあります。
そのため、血便のことを詳しく知っておくことで、自身の健康状態を把握しやすくなりますし、症状の悪化も最小限に抑えやすくなります。
したがって、便は健康のバロメーターともいえるのです。