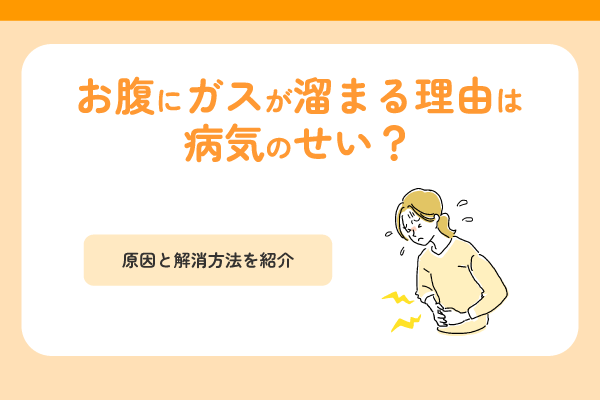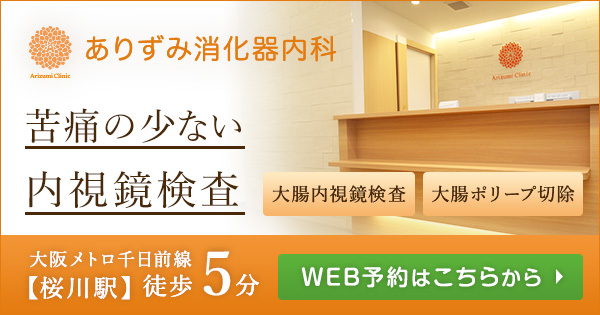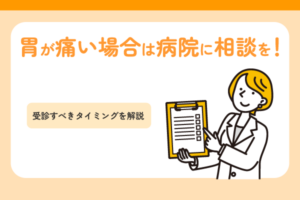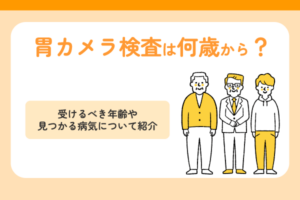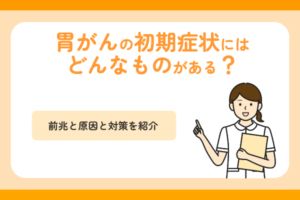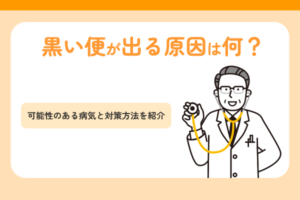「お腹にガスが溜まっている気がするが、便秘なのだろうか?」
「お腹が張っているのはお腹にガスが溜まっているからなの?」
お腹が膨れているように感じ、苦痛を感じている場合、それはお腹にガスが溜まっているのが理由だからかもしれません。
人のお腹は、様々な理由でガスが発生します。
そのガスの量が多い、あるいは発生したガスが排出されない場合、膨満感といって、お腹の張りや苦痛を感じやすくなります。
お腹にガスが溜まる理由は病気の可能性もありますが、主に生活習慣や食事スタイルが原因です。
しかし、病気が原因じゃなくてもお腹にガスが溜まりやすいような生活習慣の場合、病気に発展するおそれがあります。
この記事では、お腹にガスが溜まる理由や、病気が原因で考えられる膨満感、そして解消方法を紹介します。
膨満感にお悩みの場合はご参考ください。
- お腹にガスが溜まる理由
- 病気の場合の病名
- お腹のガスが溜まっている場合の対処方法
お腹にガスが溜まる主な原因
お腹にガスが溜まる主な原因は、以下の4つが挙げられます。
- 空気を多く飲み込んでいる
- 食生活が肉食中心
- 便秘によりガスが排出されにくい
- 病気よって腸のガス排出力が弱まっている
ここでは1この4つの原因のメカニズムを詳細に紹介いたします。
食事の際に空気も多く飲み込んでしまっている
お腹にガスが溜まる原因のひとつが「空気の飲み込みすぎ」です。
この現象は医学的には「呑気症(どんきしょう)」いう状態に分類されます。
通常、食物を飲み込む際にはある程度の空気が一緒に入りますが、食べ方や生活習慣によって空気の摂取量が大幅に増えることがあります。
以下の表に、空気を過剰に飲み込みやすい行動とその要因をまとめます。
| 空気を飲み込みやすくする行動 | 背景や影響 |
|---|---|
| 早食い | 咀嚼回数が少なくなり、唾液や空気と一緒に食物を飲み込む頻度が増える |
| 会話をしながらの食事 | 話す際の呼吸動作が空気の取り込みと重なり、嚥下回数も増加する |
| 飲食中の姿勢が悪い | 背中を丸めた姿勢や猫背により、食道の通過が不安定になり空気を含みやすくなる |
| ガムや飴の常習 | 唾液を頻繁に飲み込む過程で空気も取り込まれやすくなる |
現代の忙しいライフスタイルでは、昼休みに急いで食事を済ませることや、スマートフォンを見ながらの“ながら食い”は、空気の飲み込みを助長する一因です。
例えば、スマホを見ながら食事をする際猫背になりやすく、その影響で空気を含みやすくなります。
また、仕事中の眠気覚ましのガムや、ダイエットで甘いものを抑えていたり、禁煙で口さみしい状態に飴を舐めていると、空気を取り込みやすくなり、呑気症を招きます。
このように、空気を無意識に飲み込む習慣は腸内にガスを蓄積させやすくし、お腹の張りやげっぷ、腹部不快感といった症状につながるのです。
肉を中心とした食生活を送っている
肉類を中心とした食生活は、お腹にガスが溜まりやすくなる大きな要因です。
特に動物性たんぱく質や脂肪分の多い食品を多く摂取すると、腸内環境に悪影響を与え、ガスの発生量が増加します。
肉に多く含まれる動物性たんぱく質は、胃や小腸で完全に分解されなかった場合、大腸に届くと腸内細菌による「腐敗型発酵」が起こります。
この発酵の過程でガスが発生してしまうため、肉食中心の場合、発生するガスの量も増加してしまうのです。
以下の表は、肉類中心の食事がガス発生に与える影響を要因別に整理したものです。
| 肉中心食の特徴 | ガスが増える理由 |
|---|---|
| 動物性たんぱく質が多い | 分解しきれなかった成分が腸内で発酵・腐敗し、悪臭ガスを生成 |
| 脂肪分が多い(脂身・揚げ物など) | 消化に時間がかかるため、腸内での停滞が長くなり、ガスが蓄積しやすくなる |
| 食物繊維の摂取が少なくなりがち | 善玉菌が減少し、腸内環境が悪化、ガスを産生する悪玉菌が増加しやすくなる |
さらに、肉ばかりを食べていると、自然と野菜や海藻類の摂取が減るため、腸内の善玉菌が好む栄養が不足しがちになり、腸内環境のバランスが崩れやすくなります。
その結果、肉類を分解発行させてガスを多く作り出す悪玉菌が優位になり、張りや膨満感といった症状が慢性的に続くようになるのです。
便秘によりガスが多く発生している
便秘は、お腹にガスが溜まりやすくなる代表的な原因のひとつです。
肉食中心の生活でも、便通に問題なければきちんと排出されるため、お腹にガスが溜まることは少ないです。
しかし、便秘によって便が腸内に長時間とどまることで、ガスは際限なく発生し続け、排出されません。
そのため、ガスが蓄積し、膨満感を覚えやすくなってしまうのです。
特に慢性的な便秘では、腸内にたまった老廃物が細菌の働きによって分解され、臭いの強いガスが大量に発生します。
便秘によるガス発生のメカニズムは、以下のとおりです。
| 状況 | ガスが増える理由 |
|---|---|
| 便が長時間腸内にとどまる | 便中の未消化成分が腸内細菌によって発酵し、ガスが大量に生成される |
| 腸のぜん動運動が低下している | 排便のスピードが遅くなり、ガスの滞留時間が長くなる |
| 悪玉菌の増殖 | 長期的な停滞により腸内環境が悪化し、ガスを多く作る菌が優勢になる |
| 排便がないことで出口がふさがる | ガスが体外へ逃げられず、腹部に蓄積して張りや不快感を強く感じるようになる |
特に女性や高齢者は、ホルモンバランスや筋力の低下によって便秘になりやすく、結果として腹部の膨張感やガスによる痛みを訴えるケースが多く見られます。
また、座りっぱなしの生活や、水分・食物繊維の不足も便秘を悪化させる要因です。
このように、便秘は単なる排便の問題ではなく、腸内の発酵環境を変化させ、ガスの発生量を増加させる根本的な原因として見逃せません。
放置すればさらに悪化し、腸内フローラのバランスにも深刻な影響を及ぼす可能性があります。
病気で腸が弱まりガスの排出量が少なくなっている
腸の機能が病気によって低下している場合、腸内で発生したガスを効率よく排出できず、腹部に溜まる原因となります。
これは腸の「ぜん動運動(腸が内容物を押し出す動き)」が弱まることで起こり、腸の通過速度が遅くなるためです。
ガスの排出経路が滞ることで、腸内にガスが留まりやすくなり、不快感や膨満感を引き起こします。
このような腸機能の低下を引き起こす主な疾患は、以下のとおりです。
| 関連する疾患 | 腸機能への影響とガス排出の妨げ |
|---|---|
| 過敏性腸症候群(IBS) | 自律神経の乱れにより腸の動きが不安定になり、ガスが溜まりやすくなる |
| 糖尿病性神経障害 | 自律神経障害によって腸のぜん動運動が低下し、排出が遅れる |
| 腸閉塞や癒着(術後など) | 腸の物理的な狭窄が生じ、ガスの移動や排出が妨げられる |
| 加齢に伴う消化機能の衰え | 筋力低下や腸の反応鈍化により、腸内容物の排出が不十分になる |
特に高齢者では、腸の筋肉の力が自然に弱くなることに加え、薬の副作用や基礎疾患が重なることで、ガス排出がさらに困難になります。
また、糖尿病患者では、自律神経障害の進行とともに腸の動きが鈍くなる「糖尿病性胃腸障害」が発症することもあり、ガスが滞留しやすくなる傾向があります。
これらの状態では、ガスそのものの発生量がそれほど多くなくても、腸内にとどまってしまうことでお腹が張る症状が強く出るのが特徴です。
腸の運動機能の低下は見えづらい変化ですが、慢性的な膨満感を感じる際には、内科や消化器内科の診察を推奨します。
お腹にガスが溜まりやすくなる病気と理由を紹介
お腹のガス溜まりには、日常の習慣だけでなく、実は病気が関与しているケースも少なくありません。
病気になることで朝の蠕動運動が弱まったり細くなったりしてしまうことで、ガスや便が排出されにくくなってしまうからです。
ここでは、お腹にガスが溜まりやすい病気とその原因について紹介します。
呑気症
- 早食い、会話をしながらの食事、炭酸飲料の常飲などの食習慣が要因のもの
- 緊張や不安によって唾液や空気を頻繁に飲み込む「空嚥下(からえんげ)」が無意識に起こることによる心因性のもの
呑気症は、上述したように無意識に空気を大量に飲み込んでしまうことで、胃や腸にガスが溜まりやすくなる病気です。
通常、人は食事や会話の際に少量の空気を一緒に飲み込みますが、呑気症ではその量が異常に増加し、腹部膨満感やげっぷ、おならの頻発といった症状が現れます。
呑気症では、胃にたまった空気が上に抜ければげっぷ、下に抜ければおならとして排出されます。
しかし排出のタイミングが不規則だったり、腸内の動きが弱まっていたりすると、ガスが留まり続け、慢性的なお腹の張りを引き起こします。
食生活の他にも、ストレスとの関連が強い点も、呑気症の特徴です。
職場や家庭での緊張が続くと、呼吸が浅くなり、口からの空気の摂取量が増えやすくなります。
心理的要因が絡むため、呑気症は単なる生活習慣病ではなく、身体と心の両面からアプローチが求められる疾患です。
基本的に命に関わる疾患ではなく、生活習慣の見直しやストレスの解消を行うことで自然と治ります。
しかし、食習慣の悪化やストレスを放置していると呑気症以外の病気を発症する恐れがあるため、軽視してはいけません
慢性胃炎
- 胃の運動機能の低下によって腸内にある食べ物の発酵時間が延びるのが要因のもの
- 消化液の分泌量が減ることで食べ物が十分に分解されず、悪玉菌によって腐敗が促進されることが要因のもの
- 胃腸全体の働きが鈍くなリ、ガスの排出量が低下するのが要因のもの
慢性胃炎は、胃の粘膜が長期間にわたって炎症を起こす状態で、胃の機能が低下し、結果として腸にガスが溜まりやすくなることがあります。
特に、ストレスやピロリ菌感染が主な原因とされており、現代人に多く見られる消化器疾患の一つです。
特にピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)の感染による慢性胃炎は、日本人に多く見られ、40歳以上では半数近くが感染しているという報告もあります。
ピロリ菌が胃の粘膜に定着すると炎症が持続的に起き、胃液の分泌が抑えられ、消化不良を引き起こします。
この結果、分解不十分な食物が大腸に達し、ガスが発生しやすくなるのです。
さらに、胃炎による痛みや不快感が食事の質や頻度にも影響し、結果的に腸の動きも悪化するという悪循環に陥ります。
こうした機能の低下が積み重なることで、ガスの蓄積と膨満感が慢性的に続く状態になりやすくなります。
大腸がん
- 腫瘍によって便通が悪化し滞留することが要因のもの
- 腸の働きの悪化による排出困難が要因のもの
- 転移・悪化によって体の機能が著しく低下することが要因のもの
大腸がんは、腸内に腫瘍が形成されることで腸管が狭くなり、便の通過が妨げられる病気です。
この通過障害が便秘を引き起こし、結果的に腸内にガスが溜まりやすくなります。
腫瘍の位置や大きさによっては、ガスの排出すら困難となり、強い膨満感や腹痛を伴うこともあります。
何より、大腸がんを発症した場合、早期の治療を行わなければお腹にガスが溜まる以上に生命に関わる事態に発展するため、早期発見早期治療が重要事項となります。
大腸がん特有のサインとして急な便秘・便の細さの変化・血便・体重減少といった症状がありますが、これらはがんが進行しなければ自覚が難しいため、最善の対処法は一年に一回程度の定期的な検査です。
消化器内科または内視鏡検査を行う専門医への受診を行い、初期段階でがんを発見しましょう。
機能性ディスペプシア
- 腸の働きの悪化による排出困難が要因のもの
- 胃腸の働きを調整する神経機能の低下が要因のもの
- 胃が過敏になり少量のガスでも膨満感を強く感じるようになるのが要因のもの
機能性ディスペプシアは、検査では異常が見つからないにもかかわらず、胃の痛みや不快感、満腹感、膨満感といった症状が続く機能性の消化障害です。
この病気では胃腸の運動機能や感受性が低下し、ガスが溜まりやすくなる体質に変化してしまいます。
大腸がんほど深刻な病気ではありませんが、この疾患の特徴は「検査で異常が見つからない」ことにあります。
しかし、人の自覚症状は非常に強く、生活の質を大きく損なう可能性があるため、心身両面のケアが必要です。
お腹にガスが溜まっている場合の解消方法
お腹にガスが溜まっている以外、体に痛みも何もない状態ならば生活習慣の見直しでごく短期間で改善が可能です。
改善と予防を行うなら生活習慣の見直しを、伊地知駅でも症状を和らげたいのであれば市販薬の使用を、医学的な方面から病気の可能性を潰したい場合は病院の診断がおすすめです。
ここでは、これら4つの改善方法について具体的に説明しましょう。
食生活とストレスの改善
ガス溜まりの改善には、腸内環境を整える食生活とストレスの軽減が不可欠です。
特に、発酵しやすい食品を控えると同時に、善玉菌を育てる食材を意識的に取り入れることが大切です。
また、ストレスも腸の動きを鈍らせる原因となるため、心のケアも並行して行う必要があります。
具体的な内容として、以下のものが挙げられます。
| 改善項目 | 対策例 |
|---|---|
| 食事内容の見直し | 発酵性糖質(FODMAP食品)を避ける、食物繊維のバランスをとる |
| 腸内環境の整備 | ヨーグルト・納豆・味噌などの発酵食品で善玉菌を増やす |
| 食事の習慣 | ゆっくり噛んで食べる、炭酸飲料・ガムの摂取を控える |
| ストレス対策 | 睡眠・入浴・マインドフルネス・趣味の時間などで心を緩める習慣をつける |
こうした食習慣と精神的安定の両立は、腸の動きを活発にし、ガスが溜まりにくい身体環境をつくります。
特に発酵性糖質(例:玉ねぎ、りんご、小麦など)を控える「低FODMAP食」は、効果的なケースが多く報告されています。
運動による腸の活性化
運動は腸の動きを促進し、ガスの自然な排出を助ける効果があります。
特に、軽めの有酸素運動やストレッチは、腸のぜん動運動を刺激し、便通を改善することでガスの発生源を減らす役割を果たします。
| 運動の種類 | 期待できる効果 |
|---|---|
| ウォーキング | 腸への適度な刺激でガスの移動を促進 |
| ヨガ(ねじりポーズ等) | 内臓マッサージ効果でガス排出がスムーズに |
| ストレッチ | 腸周辺の筋肉を緩めて、ガスの圧迫感を軽減 |
| 腹筋・体幹運動 | 腸の周囲の血流改善・ガスの滞留を防ぐ |
軽度な運動は便通の改善以外にも筋肉の柔軟性向上や、代謝の促進による美肌効果が期待できます。
寝る前に軽いストレッチを行うことで体温上昇効果を発揮し、寝入りやすくなり、快眠効果や、それに伴うストレス解消効果も期待できます。
最初は1日4~5分程度の軽いストレッチで問題ございません。
重要なのは継続することであり、毎日少量の運動でも十分な効果が期待できます。
市販薬で一時的な対処
すぐにでもお腹のガス溜まりを解消したいのであれば、市販薬もしくは処方してもらった薬を服用すれば速攻で解消できます。
食生活や運動習慣といった改善方法は、長期的に改善と予防を行うものであり、即効性を求めるのであれば一番適しているのは市販薬です。
しかし、薬と一口にいっても症状別でお腹の張りの原因は変わるので、以下の表を参考に、自分に適している薬を探しましょう。
| 薬の種類 | 作用 |
|---|---|
| 消泡剤(ジメチルポリシロキサン等) | 腸内のガス泡を細かく分解し、不快感や張りを和らげる |
| 整腸剤(ビオフェルミン等) | 善玉菌を補い、腸内環境を整えることでガスの発生を抑える |
| 下剤・便秘薬 | 便秘によるガスの蓄積が原因の場合、排便を促して解消を助ける |
お腹にガスが溜まっている原因が、食べ過ぎや最近の運動不足が原因による一時的なものであれば、市販薬だけで問題ありません。
しかし、市販薬の使用で一時的に回復しても、まだお腹の張りや膨満感が続くようであれば病院での検査が必要になります。
消化器内科での定期的な検査
お腹のガスが長期にわたり繰り返される場合は、自己対処に頼るのではなく、消化器内科での検査を受けることが重要です。
特に、便秘が続く、体重が減る、血便が見られるなどの症状がある場合は、病気の可能性を考慮すべきです。
医師による診断を受けることで、原因を明確にし、必要であれば治療を開始できます。
早期発見・早期対処が、慢性症状を防ぐ最善の方法です。
病院では、おもに以下のような検査が行われます。
| 検査の種類 | 検査でわかること |
|---|---|
| 腹部レントゲン | 腸内にたまったガスの量や位置、腸管の詰まりの有無を確認可能 |
| 内視鏡検査(大腸・胃) | 腫瘍、炎症、潰瘍などガス発生につながる病変の有無を直接観察できる |
| 血液検査 | 感染症や炎症反応、ピロリ菌感染などの兆候を把握 |
また、胃炎や胃がんの要因でもあるピロリ菌除去も病院によっては行ってくれるため、消化器内科で検査を行う場合は、そうした胃腸の治療の専門性が高いクリニックで診察を受けることをおすすめします。
まとめ
この記事では、お腹にガスが溜まる原因についての説明や、考えられる疾患、解消方法について紹介しました。
お腹にガスが溜まる原因は、空気の飲み込みすぎや肉中心の食生活、便秘、腸の機能低下といった日常的な要因から、呑気症や慢性胃炎、大腸がんなどの病気まで多岐にわたります。
原因を正しく理解し、食生活や運動、ストレス管理、市販薬の活用、必要に応じて医療機関での検査を組み合わせることで、ガスの蓄積による不快な症状を効果的に軽減できます。
繰り返す膨満感や張りを「一時的なもの」と軽視せず、自分の生活習慣や体調を見直すきっかけとして、一度病院での検査をおすすめします。